全身治療後のサルベージ手術で示された、進行肺がんの新たな長期生存の可能性
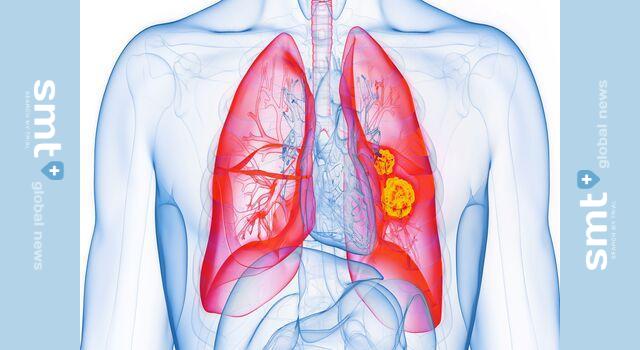
進行した非小細胞肺がん(NSCLC)では、初診時に切除不能と判断される症例が多く、治療の主軸は全身治療に置かれてきた。しかし、治療反応が良好な一部の患者に対して、全身治療後に外科切除を行うサルベージ手術の意義は十分に検討されていない。今回、全身治療後にサルベージ手術を行った高度に選択された症例を解析した結果、進行肺がんでも長期生存が現実的となる可能性が示された。研究は愛知県がんセンター呼吸器外科部の瀬戸克年氏、坂倉範昭氏らによるもので、詳細は12月17日付で「Thoracic Cancer」に掲載された。
分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬の登場により、進行NSCLCに対する全身治療成績は大きく向上している。これに伴い、初診時には切除不能と判断された症例でも、全身治療後に病変が局在化・縮小し、根治を目的としたサルベージ手術が行われるケースが増えている。一方、薬物療法後の手術は治療関連線維化など特有の課題を伴い、長期予後への真の影響については十分なエビデンスがない。こうした背景から本研究は、全身治療後にサルベージ手術を行ったNSCLC症例を後ろ向きに解析し、その安全性と腫瘍学的成績、臨床的意義を検討した。

治験情報の探し方から参加検討まで、専門スタッフが一緒にサポートします
本研究では、2014年1月1日から2024年12月31日にかけて愛知県がんセンターで治療を受けた、初診時に切除不能と診断されたNSCLC患者を対象とした。このうち、化学療法、分子標的治療、免疫療法のいずれか、またはそれらの併用後に、根治目的のサルベージ手術を受けた32例を後ろ向きに解析した。主要評価項目は全生存期間(OS)とし、副次評価項目として無再発生存期間(RFS)、重篤な合併症(Clavien–Dindo分類Ⅲa以上)、およびR0切除(完全切除)率を設定した。生存解析にはKaplan–Meier法およびlog-rank検定を用いた。
年齢中央値は61.0歳で、男性が約3分の2を占めた。ECOG Performance Status(PS)は30例が0、残る2例も1で、PS 2以上の症例は認めなかった。初診時に切除不能と判断された理由は遠隔転移が最多で、次いでN3リンパ節転移や高度N2病変などであった。手術前に行われた全身治療の治療ライン数中央値は1で、細胞障害性抗がん薬、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬が症例に応じて使用されていた。
追跡期間中央値40.1か月時点で、OSの中央値には到達せず、RFSの中央値は49.9か月であった。5年OS率は75.0%(95%信頼区間〔CI〕 51.6~88.3)、5年RFS率は46.3%(95%CI 26.3~64.2)であった。
サルベージ手術の内訳は、肺葉切除術21例(65.6%)、区域切除術6例(18.8%)、楔状切除術5例(15.6%)であり、R0切除は26例(81.3%)で達成された。
合併症は全体で4例(12.5%)に発生した。重篤な合併症は1例で、胸膜癒着術を要する遷延性気漏であった。術後90日以内の死亡は認められなかった。
さらに、術後24か月以内に再発または死亡を認めなかった症例を予後良好群(18例)、認めた症例を予後不良群(14例)とし、探索的に各因子について単変量解析を行った。その結果、腺がんのみが有意に良好な予後と関連していた(88.9% vs. 35.7%、P=0.003)。
著者らは、「初診時に切除不能と判断されたNSCLC患者において、全身治療後に行われたサルベージ手術が、安全性および有効性の両面で良好な成績を示した。追跡期間中央値40.1か月における5年OS率は75%、5年RFS率は46%であり、厳密に選択された症例では、サルベージ手術が生存期間延長を目指す治療選択肢となり得る可能性が示唆された」と述べている。
その一方で、単施設・後ろ向き研究である点に加え、全身治療のみで管理された症例や、全身治療後に外科へ紹介されたものの手術に至らなかった症例が含まれていないことから、選択バイアスの影響は否定できないとしている。このため、今後は多施設前向き研究による検証が必要であると述べている。

肺がんは初期の自覚症状が少ないからこそ、セルフチェックで早めにリスクを確かめておくことが大切です。セルフチェックリストを使って、肺がんにかかりやすい環境や生活習慣のチェック、症状のチェックをしていきましょう。


