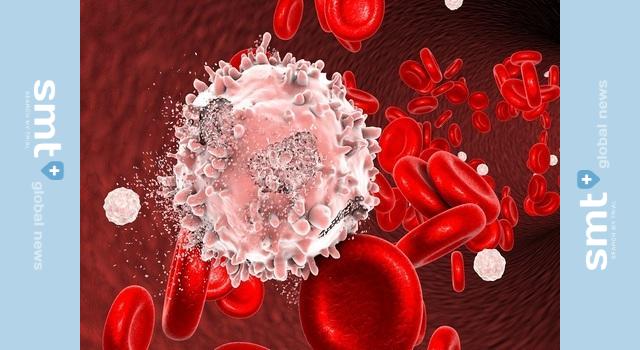-
8月 28 2023 シンデレラ体重の若年日本人女性の栄養不良の実態が明らかに
国内で増加している低体重若年女性の栄養状態を、詳細に検討した結果が報告された。栄養不良リスクの高さや、朝食欠食の多さ、食事の多様性スコア低下などの実態が明らかにされている。藤田医科大学医学部臨床栄養学講座の飯塚勝美氏らの研究によるもので、詳細は「Nutrients」に5月7日掲載された。
日本人若年女性に低体重者が多いことが、近年しばしば指摘される。「国民健康・栄養調査」からは、20歳代の女性の約20%は低体重(BMI18.5未満)に該当することが示されており、この割合は米国の約2%に比べて極めて高い。BMI18未満を「シンデレラ体重」と呼び「美容的な理想体重」だとする、この傾向に拍車をかけるような主張もソーシャルメディアなどで見られる。実際には、女性の低体重は月経異常や不妊、将来の骨粗鬆症のリスクを高め、さらに生まれた子どもの認知機能や成人後の心血管代謝疾患リスクに影響が生じる可能性も指摘されている。とはいえ、肥満が健康に及ぼす影響は多くの研究がなされているのに比べて、低体重による健康リスクに関するデータは不足している。
 治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。飯塚氏らの研究は、2022年8~9月に同大学職員を対象に行われた職場健診受診者のうち、年齢が20~39歳の2,100人(女性69.4%)のデータを用いた横断研究として実施された。まず、低体重(BMI18.5未満)の割合を性別に見ると、男性の4.5%に比べて女性は16.8%と高く、さらに極端な低体重(BMI17.5未満)の割合は同順に1.4%、5.9%だった。
次に、女性のみ(1,457人、平均年齢28.25±4.90歳)を低体重(BMI18.5未満)245人、普通体重(同18.5~25.0未満)1,096人、肥満(25.0以上)116人の3群に分類して比較すると、低体重群は他の2群より有意に若年で、握力が弱かった。栄養状態のマーカーである総コレステロールは同順に、177.8±25.2、184.1±29.2、194.7±31.2mg/dL、リンパ球は1,883±503、1,981±524、2,148±765/μLであり、いずれも低体重群は他の2群より有意に低値だった。一方、HbA1cは肥満群で高値だったものの、低体重群と普通体重群は有意差がなかった。
続いて、極端な低体重のため二次健診を受診した女性56人を対象として、より詳細な分析を施行。この集団は平均年齢32.41±10.63歳、BMI17.02±0.69であり、総コレステロール180mg/dL未満が57.1%、リンパ球1,600/μL未満が42.9%、アルブミン4mg/dL未満が5.3%を占めていた。その一方で39%の人がHbA1c5.6%以上であり、糖代謝異常を有していた。なお、バセドウ病と新規診断された患者が4人含まれていた。
20~39歳の44人と40歳以上の12人に二分すると、BMIや握力、コレステロールは有意差がなかったが、リンパ球数は1,908±486、1,382±419/μLの順で、後者が有意に低かった。また、アルブミン、コレステロール、リンパ球を基にCONUTという栄養不良のスクリーニング指標のスコアを計算すると、軽度の栄養不良に該当するスコア2~3の割合が、前者は25.0%、後者は58.3%で、後者で有意に多かった。
極端な低体重者の摂取エネルギー量は1,631±431kcal/日であり、炭水化物と食物繊維が不足と判定された人の割合が高く(同順に82.1%、96.4%)、一方でコレステロールの摂取量は277.7±95.9mgと比較的高値だった。また、28.6%は朝食を抜いていて、食事の多様性スコア(DDS)は、朝食を食べている人の4.18±0.83に比べて朝食欠食者は2.44±1.87と有意に低いことが明らかになった。
極端な低体重者は微量栄養素が不足している実態も明らかになった。例えば鉄の摂取量が10.5g/日未満やカルシウム摂取量650mg/日未満の割合が、いずれも96.4%を占めていた。血液検査からはビタミンD欠乏症の割合が94.6%に上り、ビタミンB1やB12の欠乏も、それぞれ8.9%、25.0%存在していることが分かった。さらに、40歳未満の13.6%に葉酸欠乏症が認められ、その状態のまま妊娠が成立した場合の胎児への影響が懸念された。
これらの結果に基づき著者らは、「日本人若年低体重女性は潜在的にビタミン欠乏症になりやすいことが判明した。将来の疾患リスクや低出生体重児のリスクを考えると、低体重者への食事・栄養指導が重要と考えられる」と総括している。
治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。
-
8月 28 2023 ワクチン接種回数や年齢層によるCOVID-19症状の違い――札幌市での調査で明らかに
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチン接種回数が多いほど感染時に全身症状が現れにくい一方で、咽頭痛や鼻汁などの上気道症状が現れやすいことなどが明らかになった。北海道大学医学研究院呼吸器内科の中久保祥氏らが、札幌市のCOVID-19療養判定システムなどのデータを解析した結果であり、詳細は「The Lancet Infectious Diseases」に6月30日掲載された。オミクロン株BA.2とBA.5の症状の特徴や、高齢者と非高齢者の違いも示されている。
この研究に用いられた札幌市のCOVID-19療養判定システムは2022年4月にスタートし、重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2(SARS-CoV-2)陽性判定を受けた同市市民が登録して症状などを記録している。記録されている情報は、発症日、食事摂取状況、12種類(発熱、咳、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、頭痛、倦怠感、関節や筋肉の痛み、下痢、味覚・嗅覚異常など)の症状、年齢、性別、基礎疾患など。これらの情報と、感染者等情報把握・管理支援システム、ワクチン接種記録システムのデータを統合して解析が行われた。
 COVID-19に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
COVID-19に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。解析対象は、2022年4月25日~9月25日にデータが記録されていた15万7,861人。主な特徴は、年齢が中央値33歳(四分位範囲17~47)、65歳以上6.9%、男性47.7%、BMI中央値21.1、BMI30以上4.3%、ワクチン未接種者38.0%、感染既往者3.7%など。また、オミクロンBA.2の感染者が21.8%、BA.5が78.2%を占めていた。重症化した(酸素投与と入院を要した)のは142人、30日以内の死亡は4人だった。
最も一般的な症状は咳(62.7%)であり、次いで咽頭痛(60.7%)、鼻汁(44.3%)、頭痛(42.1%)、38度以上の発熱(38.8%)、痰(36.1%)、関節や筋肉の痛み(29.1%)、食思不振(28.1%)などだった。BA.2流行期と比較してBA.5流行期には発熱や食思不振などの全身症状が多く、これはワクチン接種歴や基礎疾患などの影響を除外した解析でも同様だった。
ワクチン接種歴との関連では、3回以上接種した人は全身症状が現れにくく、反対に鼻汁や咽頭痛といった上気道症状が現れやすいことが分かった。またワクチン接種の影響は、接種日から日数が経過するに従い小さくなること、2回接種よりも3回接種の方がより強い影響が持続することも示された。
年齢との関連については、高齢者は若年者と比較して、全体的に症状が現れにくいものの、いったん発熱や倦怠感などの全身症状が出現すると、その後に重症化しやすくなる傾向が認められた。例えば、呼吸困難、発熱、食思不振、倦怠感という4症状がある場合、それらがない場合に比べて重症化のオッズ比は40.26(95%信頼区間14.60~110.98)に上った。一方で、咽頭痛や鼻汁が出現した高齢者は、その後の重症化リスクが低い傾向が見られた。例えば、咽頭痛と鼻汁の双方がある場合、その後の重症化のオッズ比は0.19(同0.08~0.45)だった。
著者らは、「これまでの研究から、SARS-CoV-2の武漢株、アルファ株、デルタ株、オミクロン株では、感染時の症状が異なることが知られていたが、オミクロン株の亜株(BA.2とBA.5)の間でも、症状の特徴が異なることが明らかになった。また、ワクチン接種者では上気道症状が現れやすくなるという点も、今回初めて示された」と総括。さらに、「高齢者では上気道症状ではなく、全身症状が重症化の前兆と考えられるという知見は、今後の治療介入の判断に有用な情報となり得る」と付け加えている。
治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。
-
8月 21 2023 メンタルヘルスケアアプリ利用で産後うつリスクが低下する可能性
メンタルヘルスケアのために開発された、スマートフォンなどで利用可能なアプリケーションが、産後うつのリスクを抑制する可能性のあることが報告された。浜松佐藤町診療所(静岡県)の三浦弓佳氏らが行った、システマティックレビューとメタ解析の結果であり、詳細は「BMC Pregnancy and Childbirth」に6月14日掲載された。
国内の妊産婦の死亡原因のトップは自殺であり、これには産後うつの影響が少なくないと考えられている。産後うつによる自殺を防ぐためには、産後うつ状態の早期診断と適切なケアが重要だが、産後には育児などのために時間的な制約が生じることや、偏見などのために、うつリスクがあるにもかかわらず受療行動を起こさない女性が少なくない。このような状況に対応して、モバイルテクノロジーを用いたメンタルヘルスケアアプリが開発されてきた。ただ、それらのアプリの有用性の検証がまだ十分でなく、特に産後うつの「治療」ではなく「予防」という視点でのエビデンスはより不足している。そこで三浦氏らは、システマティックレビューとメタ解析による検討を行った。
 うつ病に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
うつ病に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。主要アウトカムを産後うつの発症、副次的アウトカムをうつ状態の評価スケール〔エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)など〕のスコアとして、システマティックレビューとメタ解析のための優先的報告項目(PRISMA)に基づき、MEDLINE、Scopus、PsycINFO、CINAHLなどの文献データベースや国際臨床試験登録プラットフォーム(ICTRP)を用いて、無作為化比較試験の報告やレビュー論文の参考文献を2020年3月26日に検索。2023年3月17日に新たに追加された文献の有無を確認した。解析対象は、用いられたアプリ自体に自動化された心理社会的介入が含まれている研究報告とし、通話やチャットなどの通信のみを提供するアプリによる研究は除外した。また、研究参加者に精神疾患の既往者が含まれている研究も除外した。
計2,515件がヒットし、タイトルと要約に基づくスクリーニング、全文精査を経て、最終的に16件を解析対象として抽出した。メタ解析に必要なデータが不足している場合は、論文の著者に連絡を取り提供を依頼した。
16件の研究は全て2015年以降に報告されたもので、中国、ポルトガル、シンガポールから各3件、米国から2件、そのほかに日本を含む数カ国から1件ずつ報告されていた。8件は出産前から介入が開始され、ほかの8件は出産後の介入だった。介入の内容は、認知行動療法に基づくものが6件、マインドフルネスに基づくものが3件であり、そのほかには心理教育的手法によるもの、愛着理論に基づくものなどが含まれていた。
産後うつの発症への影響を検討していた研究は3件で、そのうち1件はデータが不十分であったため、2件をメタ解析の対象とした。それら2件ともに有意な影響を報告しておらず、メタ解析の結果もリスク比(RR)0.80(95%信頼区間0.62~1.04)であって非有意だった(P=0.570)。
一方、EPDSスコアへの影響は14件の研究で検討されており、それらの中でカップルを対象とした2件の研究を除外し、母親のみに介入が行われた12件をメタ解析の対象とした。12件中4件は介入によるEPDSスコアの有意な低下を報告し、ほかの8件は非有意という結果を報告していた。メタ解析の結果は、標準化平均差(SMD)-0.96(-1.44~-0.48)であり、有意な効果が示された(P<0.001)。なお、データの不均一性が高かった(I2=82%)。
以上の結果に基づき著者らは、「心理社会的介入が可能なアプリによる産後うつ発症リスクの有意な低下は認められなかったが、EPDSスコアは有意に抑制されることが確認された。アプリによる介入が産後うつの発症を予防する可能性もあると言えるのではないか」と述べている。また、新型コロナウイルス感染症のパンデミック以降、産後うつの増加が報告されていること、および、妊娠中から産褥期の感染リスク抑制のために介入可能な機会が減っていることから、「スマホやタブレットを用いた介入が今後、より注目されるようになると考えられる」と付け加えている。
治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。
-
8月 21 2023 シスタチンC/クレアチニン比で骨粗鬆症性骨折のリスクを予測可能
腎機能の指標であるシスタチンCとクレアチニンの比が、骨粗鬆症性骨折の発生リスクの予測にも利用可能とする研究結果が報告された。吉井クリニック(高知県)の吉井一郎氏らの研究によるもので、詳細は「Journal of General and Family Medicine」に4月20日掲載された。
骨粗鬆症による骨折は、生活の質(QOL)を大きく低下させ、生命予後を悪化させることも少なくない。骨粗鬆症による骨折のリスク因子として、高齢、女性、喫煙、飲酒、糖尿病などの生活習慣病、ステロイドの長期使用などが知られているが、近年、新たなリスクマーカーとして、シスタチンCとクレアチニンの比(CysC/Cr)が注目されつつある。
 骨粗鬆症に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
骨粗鬆症に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。シスタチンCとクレアチニンはいずれも腎機能の評価指標。これらのうち、クレアチニンは骨格筋量の低下とともに低値となるために腎機能低下がマスクされやすいのに対して、シスタチンCは骨格筋量変動の影響を受けない。そのため骨格筋量が低下するとCysC/Crが上昇する。このことからCysC/Crはサルコペニアのマーカーとしての有用性が示されており、さらに続発性骨粗鬆症を来しやすい糖尿病患者の骨折リスクも予測できる可能性が報告されている。ただし、糖尿病の有無にかかわらずCysC/Crが骨折のリスクマーカーとなり得るのかは不明。吉井氏らはこの点について、後方視的コホート研究により検討した。
解析対象は、2010年11月~2015年12月の同院の患者のうち、年齢が女性は65歳以上、男性は70歳以上、ステロイド長期投与患者は50歳以上であり、腰椎と大腿骨頸部の骨密度およびシスタチンCとクレアチニンが測定されていて、長期間の追跡が可能であった175人(平均年齢70.2±14.6歳、女性78.3%)。追跡中の死亡、心血管疾患や肺炎などにより入院を要した患者、慢性腎臓病(CKD)ステージ3b以上の患者は除外されている。
平均52.9±16.9カ月の追跡で28人に、主要骨粗鬆症性骨折〔MOF(椎体骨折、大腿骨近位部骨折、上腕骨近位部骨折、橈骨遠位端骨折で定義)〕が発生していた。MOF発生までの平均期間は15.8±12.3カ月だった。
単変量解析から、MOFの発生に関連のある因子として、MOFの既往、易転倒性(歩行障害、下肢の関節の変形、パーキンソニズムなど)、生活習慣病(2型糖尿病、高血圧、脂質異常症、心不全、COPD、不眠症など)、ステージ3a以上のCKDとともに、CysC/Cr高値が抽出された。年齢や性別、BMI、骨密度、飲酒・喫煙習慣、骨粗鬆症治療薬・ビタミンD・ステロイドの処方、ポリファーマシー、関節リウマチ、認知症などは、MOF発生と有意な関連がなかった。
多変量解析で有意性が認められたのは、易転倒性と生活習慣病の2項目のみだった。ただし、単変量解析で有意な因子についてROC解析に基づく曲線下面積(AUC)を検討したところ、全ての因子がMOFの有意な予測能を有することが確認された。例えば、易転倒性ありの場合のAUCは0.703(P<0.001)、生活習慣病を有する場合は0.626(P<0.01)であり、CysC/Crは1.345をカットオフ値とした場合に0.614(P<0.01)だった。また、カプランマイヤー法によるハザード比はCysC/Crが6.32(95%信頼区間2.87~13.92)と最も高値であり、易転倒性が4.83(同2.16~10.21)、MOFの既往4.81(2.08~9.39)、生活習慣病3.60(1.67~7.73)、CKD2.56(1.06~6.20)と続いた。
著者らは、本研究が単施設の比較的小規模なデータに基づく解析であること、シスタチンCに影響を及ぼす悪性腫瘍の存在を考慮していないことなどの限界点を挙げた上で、「CysC/Crが1.345を上回る場合、MOFリスクが6倍以上高くなる。CysC/CrをMOFリスクのスクリーニングに利用できるのではないか」と結論付けている。
糖尿病性腎症のセルフチェックに関する詳しい解説はこちら

糖尿病の3大合併症として知られる、『糖尿病性腎症』。この病気は現在、透析治療を受けている患者さんの原因疾患・第一位でもあり、治療せずに悪化すると腎不全などのリスクも。この記事では糖尿病性腎病を早期発見・早期治療するための手段として、簡易的なセルフチェックや体の症状について紹介していきます。
-
8月 10 2023 コロナ禍の大学生のメンタルへの影響は2021年時点の4年生が最大
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックの大学生のメンタルヘルスへの影響を、学年別に検討した結果が報告された。2021年時点の4年生に、メンタルヘルスへの影響が最も強く現れていたという。岐阜大学保健管理センターの堀田亮氏らの研究によるもので、詳細は「Psychiatry Research」7月号に掲載された。
日常生活を急変させたCOVID-19パンデミックが、人々のメンタルヘルスに大きな影響を与えたことについて、多くの研究報告がなされている。ただし、大学生のメンタルヘルスへの影響を経時的かつ学年別に比較検討した研究は見られない。一方、岐阜大学では毎年、全学生を対象に健康状態のオンライン調査を実施している。堀田氏らは今回そのデータを用いて、大学2~4年生のパンデミックによるメンタルヘルスへの影響を詳細に検討した。
 COVID-19に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
COVID-19に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。解析対象は6,441人(平均年齢20.27歳、男性48.8%)で、2~4年生がほぼ3分の1ずつを占めていた。調査の実施時期は各年の2月で、2020年は国内ではまだパンデミックに至っておらず、大学では平常の講義が行われていた。2021年はリモート講義が行われている時期で、2022年は正常に回復する段階での調査だった。
メンタルヘルス状態の評価には、大学生の心理カウンセリングのために開発された指標(CCAPS)の日本語版を用いて、過去2週間の状態をオンラインで回答してもらった。解析は、8領域のサブスケール(抑うつ、全般性不安、社会不安、食事関連の懸念、家族関係のストレス、飲酒習慣、学業ストレス、敵意)について実施。回答者が「全く当てはまらない」~「かなり当てはまる」の5段階から選択した結果を、0~4点のリッカートスコアとして判定し、スコアが高いほどストレスをより強く感じていると判断した。
調査年・学年別に解析した結果、2~4年生の全てにおいて、2021年は2020年よりCCAPSのサブスケールのスコアが総じて高く、2022年にはやや低下するという傾向が認められた。ただし、飲酒習慣を表すスコアは、いずれの学年でも2020年が最も高値であった。この点について著者らは、飲酒行動につながりやすいサークル活動やイベント開催は、2020年の春以降に減少したためではないかとの考察を述べている。
なお、2年生では食事関連の懸念が2022年、家族関係のストレスは2020年に最高値であり、3年生では食事関連の懸念が2022年に最高値という、一部の例外的な変化が認められた。ただし、4年生については飲酒習慣を除く全てのサブスケールのスコアが、2021年に最高値であり、2020年や2022年のスコアとの比較で有意差が認められた。また、2021年の4年生のスコアは、2年生や3年生よりも高値であった。例えば、2021年の抑うつスコアは2年生が0.89±0.73、3年生0.94±0.77であるのに対して4年生は1.11±0.83であり、全般性不安も同順に0.97±0.71、1.00±0.74、1.16±0.75だった。
以上に基づき著者らは、「2021年に大学2~4年生の全てでメンタルヘルスの悪化が観察され、上級学年でその傾向が強く、特に4年生で顕著だった」と結論付けている。また、本研究は「大学生の学年別にパンデミック前後の影響を比較検討した初の研究」であり、「上級学年の大学生のメンタルヘルスを適切にサポートするための公衆衛生プログラム策定に向けた基礎データとなり得る」と述べている。
治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。
-
8月 10 2023 白血球高値は高LDL-C血症の独立したリスク因子――国内の縦断的研究
白血球数が高いことが、悪玉コレステロール(LDL-C)が高いことの独立したリスク因子であることを示すデータが報告された。福岡大学医学部衛生・公衆衛生学教室の奥津翔太氏、有馬久富氏らの研究結果であり、詳細は「Scientific Reports」に5月22日掲載された。
高LDL-C血症は心血管疾患(CVD)の確立されたリスク因子であり、LDL-Cを下げることでCVDリスクが低下することも、確固たるエビデンスにより支持されている。LDL-C上昇につながる要因としては、加齢、肥満、運動不足、トランス脂肪酸の過剰摂取などが知られている。近年、これらに加えて白血球数が高いことも、LDL-C上昇と関連がある可能性が報告されているが、いまだ明確になっていない。奥津氏らは、一般住民の健診データを用いた縦断的研究により、この点について検討した。
 高コレステロール血症に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
高コレステロール血症に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。解析には、長崎県壱岐市で行われたアテローム性動脈硬化症と慢性腎臓病に関する疫学調査(ISSA-CKD研究)のデータを用いた。2008~2017年の間に健診を2回以上受けていて、縦断的な解析が可能な30歳以上の人のうち、ベースライン時(初回の健診時)に高LDL-C血症でなく、白血球数などのデータ欠落のない3,312人を解析対象とした。なお、高LDL-C血症はLDL-C140mg/dL以上または脂質低下薬の処方で定義した。
平均4.6年の追跡で698人が高LDL-C血症を新たに発症。1,000人年当たりの罹患率は46.8だった。ベースラインの白血球数の四分位数で4群に分けると、第1四分位群は1,000人年当たり38.5、第2四分位群は47.7、第3四分位群は47.3、第4四分位群は52.4であり、白血球数が高いほど高LDL-C血症の罹患率が高いという有意な関連が認められた(傾向性P=0.012)。
次に、解析結果に影響を及ぼし得る因子(年齢、性別、喫煙・飲酒・運動習慣、肥満、高血圧、糖尿病)の影響を調整後、第1四分位群を基準として他群の罹患率を比較。すると、第2四分位群は非有意ながら〔ハザード比(HR)1.24(95%信頼区間0.99~1.54)〕、第3四分位群〔HR1.29(同1.03~1.62)〕と第4四分位群〔HR1.39(同1.10~1.75)〕は有意にハイリスクであり、ベースラインの白血球数と高LDL-C血症罹患率との間に、粗解析と同様、有意な正の関連が認められた(傾向性P=0.006)。
続いて、年齢(65歳未満/以上)、性別、肥満の有無、喫煙・運動習慣の有無、糖尿病の有無で層別化して解析。その結果、いずれについても交互作用は非有意であり、白血球数と高LDL-C血症罹患率との正の関連は、一貫したものだった。
以上より論文の結論は、「日本人の一般成人において、白血球数が高いことと高LDL-C血症リスクの高さとの関連が認められた」とまとめられている。著者らによると、白血球数と高LDL-C血症との関連を示すエビデンスはこれまで主としてアジア人を対象とする研究から示されてきていて、その理由として「食習慣の違いなどによって、アジア人は欧米人より総じて炎症レベルが低いことが関与している可能性がある」としている。ただし、この点の確認のために多くの人種/民族での同様の研究が必要とされ、また、白血球数が高いことを根拠とする治療介入の強化がCVD転帰の改善に結びつくのかという点も、今後の研究課題として挙げている。
治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。
HOME>8月 2023