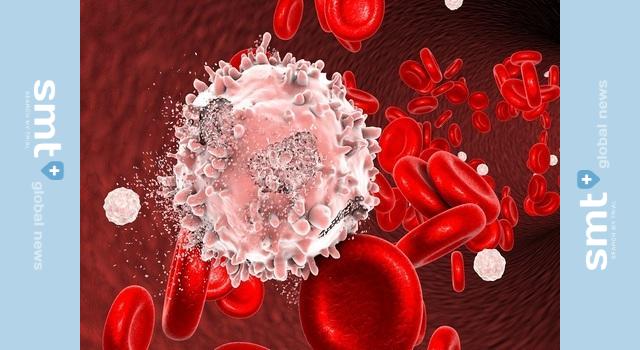-
6月 12 2024 CVD患者のフレイルと「アクティブな趣味」の関係
心血管疾患(CVD)で入院した患者のうち、入院前にアクティブな趣味を持っていた患者は、退院時のフレイルのリスクが低いという研究結果が発表された。一方で、入院前に趣味があったとしても、その趣味がアクティブなものでなければ、リスクの低下は見られなかったという。これは飯塚病院リハビリテーション部の横手翼氏らによる研究であり、「Progress in Rehabilitation Medicine」に2月22日掲載された。
趣味を持つことと死亡や要介護のリスク低下との関連を示す研究はこれまでに報告されており、入院中の運動不足で身体機能が低下しやすいCVD患者でも、趣味を持つことが身体機能の維持やフレイルの予防に役立つと考えられる。そこで著者らは、入院前に行っていた趣味と退院時のフレイルとの関連について、趣味の内容にも着目して検討した。
 心不全に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
心不全に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。研究対象は、2019年1月~2023年6月に飯塚病院に入院し、その後自宅に退院したCVD患者のうち、入院前から日常生活の介助を要する患者などを除いた269人(平均年齢68.4±11.5歳、男性72.2%)。対象患者のCVD・手術には、心不全、心筋梗塞、狭心症、冠動脈バイパス術、大動脈弁置換術、僧帽弁形成術、大動脈グラフト置換術が含まれた。
患者の状態が安定した後、入院前の趣味に関する情報を入手し、身体活動を伴う趣味(スポーツ、買い物、旅行など)を「アクティブな趣味」、それ以外の趣味(テレビ・映画鑑賞、スポーツ観戦、楽器演奏など)を「非アクティブな趣味」、趣味のない場合は「無趣味」に分類した。フレイルについては退院前日に、日本語版フレイル基準(J-CHS基準)の5項目(筋力低下、歩行速度低下、疲労感、体重減少、身体活動低下)により評価。3項目以上に該当する人を「フレイル」、1~2項目に該当する人を「プレフレイル」に分類した。
その結果、無趣味群(77人)ではプレフレイルの割合が61.4%、フレイルの割合が22.9%、非アクティブな趣味群(64人)では同順に53.2%、37.1%、アクティブな趣味群(128人)では同順に57.4%、13.9%だった。
次に、患者背景の差(年齢、性別、BMI、疾患、入院期間、就労状況、入院時の左室駆出率、入院前のフレイル)を調整して解析すると、アクティブな趣味群は、プレフレイルまたはフレイルのオッズ低下と有意に関連していることが明らかとなった(無趣味群と比較したオッズ比0.41、95%信頼区間0.17~0.90)。一方、非アクティブな趣味群ではこの関連は認められなかった(同1.56、0.52~4.64)。また、アクティブな趣味群では無趣味群と比べて、J-CHS基準の5項目のうち、歩行速度低下、疲労感、身体活動低下のオッズが有意に低かった。
以上から著者らは、「入院前にアクティブな趣味を持っていた患者は、趣味のない患者と比べて退院時にフレイルとなるリスクが低かった。一方で、非アクティブな趣味を持っていた患者では、リスクの低下は認められなかった」と結論。また、アクティブな趣味と疲労感の低下が関連していたことの説明の一つとして、アクティブな趣味を持つことが、入院中のリハビリテーションや理学療法への動機付けとなり、身体機能の維持に寄与する可能性があるとしている。
慢性心不全のセルフチェックに関する詳しい解説はこちら

心不全のセルフチェックに関連する基本情報。最善は医師による診断・診察を受けることが何より大切ですが、不整脈、狭心症、初期症状の簡単なチェックリスト・シートによる方法を解説しています。
-
8月 10 2023 白血球高値は高LDL-C血症の独立したリスク因子――国内の縦断的研究
白血球数が高いことが、悪玉コレステロール(LDL-C)が高いことの独立したリスク因子であることを示すデータが報告された。福岡大学医学部衛生・公衆衛生学教室の奥津翔太氏、有馬久富氏らの研究結果であり、詳細は「Scientific Reports」に5月22日掲載された。
高LDL-C血症は心血管疾患(CVD)の確立されたリスク因子であり、LDL-Cを下げることでCVDリスクが低下することも、確固たるエビデンスにより支持されている。LDL-C上昇につながる要因としては、加齢、肥満、運動不足、トランス脂肪酸の過剰摂取などが知られている。近年、これらに加えて白血球数が高いことも、LDL-C上昇と関連がある可能性が報告されているが、いまだ明確になっていない。奥津氏らは、一般住民の健診データを用いた縦断的研究により、この点について検討した。
 高コレステロール血症に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
高コレステロール血症に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。解析には、長崎県壱岐市で行われたアテローム性動脈硬化症と慢性腎臓病に関する疫学調査(ISSA-CKD研究)のデータを用いた。2008~2017年の間に健診を2回以上受けていて、縦断的な解析が可能な30歳以上の人のうち、ベースライン時(初回の健診時)に高LDL-C血症でなく、白血球数などのデータ欠落のない3,312人を解析対象とした。なお、高LDL-C血症はLDL-C140mg/dL以上または脂質低下薬の処方で定義した。
平均4.6年の追跡で698人が高LDL-C血症を新たに発症。1,000人年当たりの罹患率は46.8だった。ベースラインの白血球数の四分位数で4群に分けると、第1四分位群は1,000人年当たり38.5、第2四分位群は47.7、第3四分位群は47.3、第4四分位群は52.4であり、白血球数が高いほど高LDL-C血症の罹患率が高いという有意な関連が認められた(傾向性P=0.012)。
次に、解析結果に影響を及ぼし得る因子(年齢、性別、喫煙・飲酒・運動習慣、肥満、高血圧、糖尿病)の影響を調整後、第1四分位群を基準として他群の罹患率を比較。すると、第2四分位群は非有意ながら〔ハザード比(HR)1.24(95%信頼区間0.99~1.54)〕、第3四分位群〔HR1.29(同1.03~1.62)〕と第4四分位群〔HR1.39(同1.10~1.75)〕は有意にハイリスクであり、ベースラインの白血球数と高LDL-C血症罹患率との間に、粗解析と同様、有意な正の関連が認められた(傾向性P=0.006)。
続いて、年齢(65歳未満/以上)、性別、肥満の有無、喫煙・運動習慣の有無、糖尿病の有無で層別化して解析。その結果、いずれについても交互作用は非有意であり、白血球数と高LDL-C血症罹患率との正の関連は、一貫したものだった。
以上より論文の結論は、「日本人の一般成人において、白血球数が高いことと高LDL-C血症リスクの高さとの関連が認められた」とまとめられている。著者らによると、白血球数と高LDL-C血症との関連を示すエビデンスはこれまで主としてアジア人を対象とする研究から示されてきていて、その理由として「食習慣の違いなどによって、アジア人は欧米人より総じて炎症レベルが低いことが関与している可能性がある」としている。ただし、この点の確認のために多くの人種/民族での同様の研究が必要とされ、また、白血球数が高いことを根拠とする治療介入の強化がCVD転帰の改善に結びつくのかという点も、今後の研究課題として挙げている。
治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。
HOME>心血管疾患