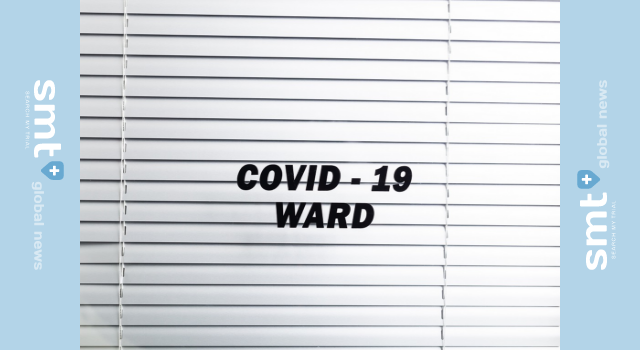-
7月 31 2023 主要な精神疾患に伴う抑うつ症状に主観的な不眠が関与
精神疾患の患者に高頻度で見られる抑うつ症状に、不眠が影響を及ぼしていることを表すデータが報告された。大うつ病性障害だけでなく、統合失調症や不安症などの主要な精神疾患の抑うつ症状が不眠と関連しており、そのことが疾患の重症度に影響を及ぼしている可能性も考えられるという。日本大学医学部精神医学系の中島英氏、金子宜之氏、鈴木正泰氏らの研究によるもので、「Frontiers in Psychiatry」に4月24日掲載された。
精神疾患で現れやすい抑うつ症状は、生活の質(QOL)や服薬アドヒアランスの低下、飲酒行動などにつながるだけでなく、自殺リスクの上昇との関連も示唆されている。一方、精神疾患に不眠が併存することが多く、大うつ病性障害(MDD)患者では不眠への介入によって抑うつ症状も改善することが報告されている。ただし、MDD以外の精神疾患での抑うつ症状と不眠の関連はよく分かっていない。MDDと同様にほかの精神疾患でも抑うつ症状と不眠が関連しているのであれば、不眠への介入によって抑うつ症状が改善し、予後に良好な影響が生じる可能性も考えられる。鈴木氏らはこの仮説に基づき、以下の検討を行った。
 うつ病に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
うつ病に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。この研究は、うつ病の客観的評価法を確立するために行われた研究の患者データを用いて行われた。解析対象は、日本大学医学部附属板橋病院と滋賀医科大学医学部附属病院の2017年度の精神科外来・入院患者のうち、研究参加に同意し解析に必要なデータがそろっている144人。疾患の内訳は、MDDが71人、統合失調症25人、双極性障害22人、不安症26人。
不眠は、アテネ不眠尺度(AISスコア)を用いた主観的な評価(24点中6点以上を臨床的に有意な不眠と定義)、および睡眠脳波検査による客観的な評価によって判定した。抑うつ症状の評価には、ベック抑うつ質問票を用い、研究目的から睡眠に関する項目を除外したスコア(mBDIスコア)で評価した。mBDIスコアは高値であるほど抑うつ症状が強いと判定される。このほか、各疾患の症状評価に一般的に用いられているスケールによって重症度を評価した。
AISスコアで評価した臨床的に有意な主観的不眠は全体の66.4%であり、疾患別に見るとMDDでは77.1%、統合失調症で36.0%、双極性障害で63.6%、不安症で69.2%だった。不眠の有無でmBDIスコアを比較すると、以下のように4疾患のいずれも、不眠のある群の方が有意に高値だった。MDDでは25.6±10.7対12.1±6.9(P<0.001)、統合失調症では22.8±8.6対11.1±7.0(P=0.001)、双極性障害では28.6±9.5対14.5±7.4(P=0.009)、不安症では23.9±10.4対12.5±8.8(P=0.012)。
一方、睡眠脳波検査から客観的に不眠と判定された割合は78.0%だった。疾患別に客観的不眠の有無でmBDIスコアを比較した結果、統合失調症でのみ有意差が認められた(18.1±9.3対9.9±7.1、P=0.047)。
次に、抑うつ症状と各精神疾患の重症度の関連を検討した。すると、mBDIスコアと統合失調症の重症度(PANSSスコア)との間に、正の相関が認められた(r=0.52、P=0.011)。これは、抑うつ症状が重度であるほど、統合失調症の症状も重いことを意味する。同様に、mBDIスコアと不安症の状態不安(一過性の不安を評価するSTAI-Iスコア)との関係はr=0.63(P=0.001)、特性不安(不安を抱きやすい傾向を評価するSTAI-IIスコア)との関係はr=0.81(P=<0.001)であり、いずれも有意な正の相関が認められた。
著者らは以上の結果を、「MDDだけでなく主要な精神疾患の全てで、主観的な不眠と抑うつ症状との関連が認められた」とまとめるとともに、「不眠に焦点を当てた介入によって、精神疾患の予後を改善できる可能性があり、今後の研究が求められる。例えば、各精神疾患の治療において、鎮静作用を有する薬剤を選択することが予後改善につながるかもしれない」と述べている。
なお、不眠の客観的な評価よりも主観的な評価の方が、より多くの精神疾患の抑うつ症状に有意差が観察されたことに関連し、「病状に対する悲観的な認識が睡眠状態の過小評価につながった可能性が考えられるが、抑うつ症状に関連した睡眠障害を検出するという目的では、主観的評価の方が適しているのではないか」との考察を加えている。
治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。
-
7月 31 2023 Long COVIDは頭痛の有無でQOLが異なる
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)急性期以降にさまざまな症状が遷延している状態、いわゆる「long COVID」の病状を、頭痛に焦点を当てて詳細に検討した結果が報告された。頭痛を有する患者はオミクロン株流行以降に増加したこと、年齢が若いこと、生活の質(QOL)がより大きく低下していることなどが明らかになったという。岡山大学大学院医歯薬学総合研究科総合内科学分野の大塚文男氏の率いる診療・研究チームによるもので、「Journal of Clinical Medicine」に5月18日掲載された。
この研究は、岡山大学病院総合内科・総合診療科に設けられている、コロナ・アフターケア(CAC)外来を2021年2月12日~2022年11月30日に受診した患者から、研究参加への不同意、年齢が10歳未満、データ欠落などに該当する人を除外した482人を対象とする、後方視的観察研究として行われた。Long COVIDは、COVID-19感染から4週間以上経過しても何らかの症状が持続している状態と定義した。
 COVID-19に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
COVID-19に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。解析対象の4分の1弱に当たる113人(23.4%)が受診時に頭痛を訴えていた。頭痛の有無で二分し比較すると、頭痛あり群は年齢が若いこと〔中央値37(四分位範囲22~45)対42(28~52)歳、P<0.01〕以外、性別の分布、BMI、喫煙・飲酒習慣に有意差はなかった。COVID-19急性期の重症度についても、両群ともに軽症が8割以上を占めていて、有意差はなかった。また採血検査の結果は、炎症マーカー、凝固マーカーも含めて、主要な項目に有意差が認められなかった。
その一方、COVID-19罹患の時期を比較すると、頭痛なし群はデルタ株以前の流行時に罹患した患者が53.9%と過半数を占めていたのに対して、頭痛あり群ではオミクロン株出現以降に罹患した患者が61.1%を占めていた(P<0.05)。また、頭痛なし群ではCOVID-19罹患から平均84日後にCAC外来を受診していたが、頭痛あり群では約2週間早く外来紹介されていた(P<0.01)。
頭痛以外の症状の有病率を比べると、以下に挙げるように、頭痛あり群の方が有病率の高い症状が複数認められた(以下の全てがP<0.05)。倦怠感(76.1対54.7%)、不眠症(36.2対14.9%)、めまい(16.8対5.7%)、発熱(9.7対3.8%)、胸痛(5.3対1.1%)。一方、嗅覚障害の有病率は、頭痛あり群の方が有意に低かった。
次に、さまざまな症状の主観的評価指標〔抑うつ症状(SDS)、胃食道逆流症(FSSG)、倦怠感(FAS)〕のスコアを見ると、それらのいずれも、頭痛あり群で症状が有意に強く現れていることを示しており、QOLの評価指標(EQ-5D-5L)は頭痛あり群の方が有意に低かった(P<0.01)。
続いて、EQ-5D-5Lスコア0.8点未満をQOL障害と定義して、多変量解析にて独立して関連する症状を検討。その結果、最もオッズ比(OR)の高い症状は頭痛であることが明らかになった〔OR2.75(95%信頼区間1.55~4.87)〕。頭痛のほかには、しびれ〔OR2.64(同1.33~5.24)〕、倦怠感〔OR2.57(1.23~5.34)〕、不眠症〔OR2.14(1.24~3.70)〕などがQOL低下と独立した関連があり、反対に嗅覚障害は唯一、負の有意な関連因子として抽出された〔OR0.47(0.23~1.00)〕。
著者らは本研究の限界点として、単一施設での後方視的研究であるため解釈の一般化が制限されること、頭痛の臨床像が詳しく検討されていないことなどを挙げている。その上で、「頭痛はlong COVIDの最も深刻な症状の一つであり、単独で出現することもあれば、ほかの多くの症状と併存することもある。頭痛がほかの症状の主観的評価に悪影響を及ぼす可能性もあり、long COVIDの治療に際しては頭痛への対処も優先すべきではないか」とまとめている。
治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。
-
7月 24 2023 生活習慣と呼吸器疾患による死亡リスクとの関係が明らかに
特定健診データを利用した解析から、生活習慣と呼吸器疾患による死亡リスクとの関連が明らかになった。喫煙習慣の有無にかかわらず、身体活動の低下は呼吸器疾患関連死の独立したリスク因子である可能性などが示された。山形大学医学部第一内科の井上純人氏らの研究によるもので、詳細は「Scientific Reports」に5月22日掲載された。
生活習慣と心血管代謝性疾患リスクとの関連については数多くの研究がなされているが、呼吸器疾患については、喫煙と肺がんやCOPD(慢性閉塞性肺疾患)の関連を除いてほとんど明らかにされていない。これを背景として井上氏らは、2008~2010年の7都道府県の特定健診受診者、66万4,926人のデータを用いた縦断的解析により、生活習慣と呼吸器疾患による死亡リスクとの関連を検討した。
 治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。解析対象者の主な特徴は、平均年齢62.3±8.8歳、男性42.76%、BMI23.4±3.5、喫煙者15.56%、習慣的飲酒者46.50%。7年間の追跡で8,051人の死亡が記録されていた。死因のトップは悪性新生物で4,159人(51.66%)であり、呼吸器疾患は437人(5.43%)で4位だった。死因としての呼吸器疾患には、ウイルスまたは細菌感染症(202人)、間質性肺炎(126人)、閉塞性肺疾患(42人)、誤嚥(30人)などが含まれていた。
悪性新生物の中の「気管支及び肺の悪性新生物」による死亡(826人)を加えた計1,263人を「呼吸器疾患による死亡」として、特定健診の健診項目データとの関連を検討すると、単変量解析では、高齢、男性、収縮期血圧高値、喫煙・飲酒習慣などが、オッズ比上昇と有意な関連があり、反対にBMI高値や運動習慣はオッズ比低下と有意な関連が認められた。
単変量解析で有意な関連が認められた因子を説明変数とする多変量解析の結果、呼吸器疾患による死亡リスクに正の独立した関連のある因子とそのハザード比(HR)は、高齢(1歳ごとに1.106)、男性(3.750)、喫煙習慣(1.941)、HbA1c(1%高いごとに1.213)、尿酸(1mg/dL高いごとに1.056)、尿蛋白陽性(1.432)、および脳血管疾患の既往(1.623)となった。反対に、負の独立した関連因子は、BMI(1高いごとに0.915)、運動習慣(0.839)、飲酒習慣(0.617)、歩行速度が速いこと(0.518)、LDL-コレステロール(1mg/dL高いごとに0.995)だった。
次に、「気管支及び肺の悪性新生物による死亡」を除く437人で多変量解析を行うと、高齢(1.141)、男性(3.898)、HbA1c(1.241)、尿酸(1.066)、尿蛋白陽性(1.876)、eGFR(1mL/分/1.73m2高いごとに1.006)および脳血管疾患の既往(2.049)が正の独立した関連因子、BMI(0.831)、運動習慣(0.591)、歩行速度が速いこと(0.274)、LDL-コレステロール(0.995)が負の独立した関連因子として抽出された。喫煙習慣や飲酒習慣は、単変量解析の段階で有意な関連が示されなかった。
続いて、「気管支及び肺の悪性新生物による死亡」の826人のみで多変量解析を行うと、独立した正の関連因子は、高齢(1.096)、男性(3.607)、喫煙習慣(3.287)、HbA1c(1.209)であり、独立した負の関連因子は歩行速度が速いこと(0.629)とヘモグロビン(1g/dL高いごとに0.884)が抽出された。
著者らは、上記3パターンの解析のいずれにおいても、運動習慣を有することや歩行速度が速いことと死亡リスクの低さとの強い関連が認められたことから、「日本人60万人以上を対象とする大規模なサンプルを用いた解析から、喫煙習慣の有無にかかわらず、運動は呼吸器疾患による死亡リスクを抑制するための重要な因子と考えられる」とまとめている。
治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。
-
7月 24 2023 糖尿病予備群は食後高血糖是正により心血管転帰が改善――介入後10年間の観察研究
食後高血糖への介入が転帰改善につながる可能性を示唆するデータが報告された。国内で実施された多施設共同研究「DIANA研究」終了後の追跡観察調査が行われ、国立循環器病研究センター心臓血管内科部門冠疾患科の片岡有氏らによる論文が、「Journal of Diabetes and its Complications」5月号に掲載された。
糖尿病では食後のみでなく食前の血糖値も高くなるが、糖尿病予備群と言われる75gブドウ糖負荷試験にて診断可能な耐糖能異常(impaired glucose tolerance;IGT)や初期の糖尿病は、食前の血糖値は正常だが食後の高血糖を伴う。食後の高血糖は心血管疾患発症のリスク因子であることを示唆する多くの疫学研究結果が報告されている。しかしながら、食後高血糖への治療介入により、心血管疾患発症リスクが抑制されるかという点については、いまだ十分に明らかになっていない。
 糖尿病に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
糖尿病に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。大阪府済生会富田林病院の宮崎俊一氏は、冠動脈疾患(CAD)を合併したIGTあるいは初期糖尿病患者を対象として、食後高血糖を改善させる薬剤による冠動脈硬化の進展抑制効果を食事・運動療法と比較する前向き無作為化試験「DIANA研究」を実施した。その研究では、食事・運動療法と比較して1年間の食後高血糖に対する薬物治療の冠動脈硬化進展抑制効果は認められなかった。しかしながら、薬物あるいは食事・運動療法いずれの治療下においても、治療開始から1年後に食後高血糖が改善していた症例は、冠動脈硬化進展が有意に抑制されていた。今回の報告は、DIANA研究終了後に実施された追跡観察調査の結果であり、1年間の食後高血糖への治療介入が、その後の約10年間の心血管疾患発症に及ぼす効果について検討された。
DIANA研究では302人の患者を、α-グルコシダーゼ阻害薬(ボグリボース)群、グリニド薬(ナテグリニド)群、あるいは食事・運動療法群の3群に無作為に割り付け、1年間の介入終了後は主治医の裁量による治療が継続されていた。このうち、243人が追跡調査の解析対象とされ、その平均年齢は64.6±9.3歳、女性が13.6%であり、IGTが58.9%、初期の2型糖尿病は41.1%であった。主要評価項目は、観察期間中の全死亡、非致死性心筋梗塞、緊急冠動脈血行再建術を含めた主要心血管イベント(MACE)の発生率と定義された。
中央値9.8年(範囲7.1~12.8)の観察期間におけるMACE発生件数は91件であった。DIANA研究において食後血糖改善を目指した薬物治療群のMACE発生率は、食事・運動療法群と有意差を認めなかった〔ボグリボース群はハザード比(HR)1.07(95%信頼区間0.69~1.66)、ナテグリニド群はHR0.99(同0.64~1.55)〕。MACEを構成する全死亡、非致死性心筋梗塞、血行再建術それぞれの発生率についても、薬物治療群と食事・運動療法群の間に有意差は見られなかった。IGT、初期糖尿病それぞれにおいても、薬物治療群のMACE発生率は食事・運動療法群と同等であった。
本研究では、薬物あるいは食事・運動療法いずれの治療下においても、治療開始から1年後における糖代謝改善の有無(IGTから正常耐糖能への変化、糖尿病からIGTあるいは正常耐糖能への変化)により対象症例を2群に分類しMACEの発生率が比較された。対象症例の55.9%は糖代謝改善を認めたが、MACE発生率は非改善群と有意差を認めなかった〔HR0.78(0.51~1.18)〕。
対象症例を、IGT、初期糖尿病に層別化して検討を行った。IGTの症例においては、IGTから正常耐糖能へ改善していた群は、非改善群に比して観察期間中のMACE発生率が有意に低率であった〔HR0.55(0.31~0.97)〕。年齢、性別、インスリン抵抗性(HOMA-IR)、血圧、スタチンやβ遮断薬使用を調整後も、結果は同様であった〔HR0.44(0.23~0.86)〕。
一方、初期糖尿病症例では、IGTあるいは正常耐糖能へ改善していた群のMACE発生率は、非改善群と比較して有意差を認めなかった〔HR1.49(0.70~3.19)〕。著者らは本研究の限界点として、post-hocの事後解析であること、無作為化割り付けによる介入期間が1年間と比較的短いこと、観察期間中の糖代謝の変化のデータは収集していないことなどを挙げている。α-グルコシダーゼ阻害薬のアカルボースによる心血管イベント発生率の減少を報告した先行研究「STOP-NIDDM」は介入期間が長く、IGTのみを対象としており、CADを有する症例は4.8%のみであった。一方、本研究はCADをすでに有しているIGTあるいは初期糖尿病症例を対象としていることから、著者らは、α-グルコシダーゼ阻害薬の心血管疾患発症に対する効果が異なった可能性を述べている。これらの考察の上で論文の結論は、「CADのあるIGT患者の長期予後改善においては、正常耐糖能への改善を目指した介入治療が必要と考えられる」と記されている。
糖尿病のセルフチェックに関する詳しい解説はこちら

糖尿病でいちばん恐ろしいのが、全身に現れる様々な合併症。深刻化を食い止め、合併症を発症しないためには、早期発見・早期治療がカギとなります。今回は糖尿病が疑われる症状から、その危険性を簡単にセルフチェックする方法をご紹介します。
-
7月 19 2023 国内COVID-19入院患者の精神症状の実態――不眠やせん妄は重症度と相関
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による入院患者では、ほかの呼吸器疾患患者よりも精神症状発現率が高く、また一部の症状はCOVID-19重症度と相関することが明らかになった。九州大学大学院医学研究院精神病態医学の中尾智博氏らの研究によるもので、詳細は「Brain, Behavior, & Immunity – Health」5月号に掲載された。
COVID-19の後遺症、いわゆるlong COVIDでは倦怠感などの身体症状に加えて、抑うつや不安などの精神症状が高頻度に現れることが知られている。一方、COVID-19急性期の精神症状については大規模研究の報告が限られている。これを背景として中尾氏らは、福岡県内の9病院のDPC(診療報酬包括評価)データおよび精神科カルテデータを用いた解析から、COVID-19入院患者に発生する精神症状の実態の把握を試みた。
 COVID-19に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
COVID-19に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。2020年1月~2021年9月に、4件の大学病院、3件の国立病院機構病院、および公立病院、民間病院各1件に入院したCOVID-19患者数は2,743人(平均年齢53.7±22.7歳、女性44.3%)だった。なお、COVID-19以外の呼吸器感染症が併存している患者は除外されている。
36.1%に対して入院中に睡眠薬、11.2%に抗うつ薬、5.8%に抗不安薬が処方され、27.6%には抗うつ薬や抗不安薬およびその他の向精神薬が併用されていた。睡眠薬の処方に関連する因子を多変量解析で検討すると、年齢〔オッズ比(OR)1.03〕、糖尿病(OR1.53)、慢性腎臓病(OR1.59)が独立した因子として抽出された。また、向精神薬の処方に関連する因子の多変量解析からは、年齢(OR1.04)、糖尿病(OR1.29)、認知症(OR1.88)が有意な正の関連因子、BMIが18~25であることは有意な負の関連因子(BMI18未満と比較してOR0.56)として抽出された。
次に、入院中に精神科の介入を要した患者221人(8.1%)に着目し、この患者群をCOVID-19の重症度で分類(厚生労働省の診療の手引き第6版に基づく分類)すると、不眠やせん妄は重症度が高いほど出現頻度が高いという有意な関連が認められた。一方、不安の出現頻度はCOVID-19重症度との関連が見られなかった。
続いて、インフルエンザ入院の患者データを用いて、傾向スコアマッチングにより年齢や性別の分布、併存疾患有病率が一致する各群211人から成るデータセットを作成。両群の薬剤処方状況を比較すると、睡眠薬の処方率はインフルエンザ群が25.1%、COVID-19群が41.7%であり、後者に対して有意に多く処方されていた(P<0.001)。抗不安薬については同順に3.3%、7.6%でやはり後者で高かったが、群間差はわずかに非有意だった(P=0.054)。抗うつ薬は7.1%、10.9%だった(P=0.174)。
同様に、インフルエンザ以外の急性気道感染症と診断されていた患者データを用いて、性別の分布、併存疾患有病率が一致する各群1,656人から成るデータセットを作成(年齢はCOVID-19群の方が若年で有意差あり)。両群を比較すると、睡眠薬の処方率は急性気道感染症群37.0%、COVID-19群40.5%でやはり後者の方が有意に高く(P=0.039)、抗うつ薬についても同順に9.6%、12.9%で後者の方が高かった(P=0.003)。一方、抗不安薬は7.7%、5.9%であり、前者の方が高かった(P=0.039)。
これらの結果から論文の結論は、「COVID-19入院患者は不眠や抑うつ、不安が発症しやすく、他の呼吸器感染症より向精神薬の処方率が高かった。一部の精神症状はCOVID-19の重症度と相関していた。COVID-19は既存の感染症より精神機能へ与える影響が大きいと考えられる」とまとめられている。また考察として、「COVID-19の急性期に発症する精神症状とlong COVIDの精神症状が連続したものである可能性もある」と述べ、この点についての今後の検討の必要性を指摘している。
治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。
-
7月 19 2023 1カ月の生活習慣改善で精液の質が向上する――男性不妊外来患者の観察研究
タバコやお酒を控えたり、熱がこもりにくいタイプの下着を履く、禁欲期間が長くならないようにするといった生活習慣の見直しによって、精液の質が改善する可能性を示す研究結果が報告された。不妊外来を受診した男性に対してこのような指導を行ったところ、約1カ月後に精子の運動能の有意な向上などが確認されたという。千葉大学大学院医学研究院泌尿器科学・亀田IVFクリニック幕張の小宮顕氏らの研究によるもので、詳細は「Heliyon」に4月4日掲載された。
男性不妊の一因として不適切な生活習慣や慢性疾患の影響が関与していることが知られている。また、男性の生殖能力が低いことは、がんなどの疾患罹患や死亡リスクの高さ、あるいは生まれてくる子どもが早産や低出生体重児となるリスクの高さと関連しているとする報告もある。そのため、男性不妊のリスク因子の中で修正可能のものを早期に見いだして介入することが、不妊治療の成功とともに本人と子どもの健康につながる可能性もある。とはいえ、男性の生殖能力に影響を与える修正可能な因子へ介入することの効果は、いまだ明確になっていない。
 不妊症に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
不妊症に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。以上を背景として小宮氏らは、体外受精(IVF)や顕微授精を行っている生殖医療専門施設である亀田IVFクリニック幕張をカップルで受診した男性患者を対象に、生活習慣改善の指導を行って、その前後での生殖能力に関わる検査値の変化を検討した。解析対象は、初回受診時に精子の数や精液の質の低下を示す何らかの所見があり、かつ無精子症ではない402人(平均年齢35.8±5.6歳)。なお、全カップルの80.6%が原発性不妊症(過去に妊娠成立が一度もない)であり、52.9%は不妊症の女性要因ありと診断されていた。
解析対象男性の主な特徴は以下の通り。現喫煙者22.6%、習慣的飲酒者47.0%、夜間勤務者14.8%、性器に熱ストレスが加わりやすい肌に密着する下着を用いている割合が68.7%、禁欲期間が3日を超えている割合が31.2%で、性交頻度は月4回以下が75.6%、月1回以下が22.2%だった。また、生殖能力の低下に関連する可能性のある検査指標や併存疾患として、BMI30以上が7.0%、糖尿病3.4%、亜鉛欠乏症16.2%、性腺機能低下症17.0%、触知可能な精索静脈瘤25.9%、軽症以上の勃起障害(SHIMという評価スコアが21点以下のED)44.2%、中等症以上のED(SHIMが16点以下)18.8%などが認められた。患者全体の98.8%が、生殖機能低下につながる可能性のあるこれらの因子を一つ以上有していた。
生活習慣改善指導の主な内容は、タバコやアルコールをやめるか減らす、性器への熱ストレスを抑える(ゆったりとした下着を着用、パソコンを膝の上に置いて使わない、サウナや長湯を避ける)、脱毛症治療薬の服用中止、禁欲期間を最大3日以内とする(禁欲が長引くと精液の質が低下するため)など。なお、糖尿病などの併存疾患の治療は行わなかった。
初回の検査から中央値28日(平均36.1±54.3日)後に2回目の検査を実施。その間に、禁欲期間は平均3.6日から2.9日へと有意に短縮していた。検査所見については、精液量や総精子数は有意な変化が見られなかったが、精液の質を表す精子濃度、精子の運動性、総運動精子数(TMSC)は有意に上昇し、精子DNA断片化率は有意に低下していた。また、乏精子症に該当する割合は49.1%から33.6%に、精子無力症は74.8%から53.4%に、いずれも有意に減少していた。
介入前後のTMSCの差は720万だった。これを患者背景別に解析すると、35歳以上や喫煙・飲酒習慣あり、短時間睡眠(6.5時間未満)、性器への熱ストレスが生じやすい生活習慣、精液量が少ない(1.0mL未満)、軽症EDに該当する患者でも、TMSCの有意な増加が認められた。さらに、性腺機能低下症、触知可能な精索静脈瘤、脂質異常症、高尿酸血症、肝機能障害を有する患者も、介入によるTMSCの有意な増加が認められた。
その一方で、BMI30以上、高血圧、糖尿病、亜鉛欠乏症、夜間勤務、禁欲期間が3日を超える、中等症以上のEDなどに該当する患者では、TMSCの有意な変化が見られなかった。それらの因子を独立変数、介入によるTMSCの増加が720万未満であることを従属変数とする多変量回帰分析からは、中等症以上のEDのみが独立した関連因子として抽出された。
著者らは、本研究は単施設の後方視的観察研究であること、精液の質に影響を及ぼし得るビタミンDを含む栄養素摂取量を評価していないことなどの限界点があると述べた上で、「男性不妊患者に対して生活習慣の修正を指導すれば、泌尿器科での専門的治療を受ける前に、精液の質をある程度改善できるのではないか」とまとめている。
治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。
-
7月 14 2023 糖尿病腎症の病期が網膜症と黄斑浮腫の発症・重症度に関連
糖尿病腎症の病期が、糖尿病網膜症・黄斑浮腫の発症リスクおよび重症度と、独立した関連のある可能性を示すデータが報告された。JCHO三島総合病院の鈴木幸久氏、自由が丘清澤眼科(東京)の清澤源弘氏の研究によるもので、詳細は「Biomedicines」に5月22日掲載された。
かつて長年にわたって成人の失明原因のトップであった糖尿病網膜症(DR)は、近年の治療の進歩により失明を回避できることが多くなった。とはいえ、緑内障や加齢黄斑変性と並び、いまだ失明の主要原因の一角を占めている。また糖尿病ではDRが軽症であっても黄斑浮腫(DME)を生じることがある。黄斑は眼底の中央に位置し視力にとって重要な網膜であるため、ここに浮腫(むくみ)が生じるDMEでは視力が大きく低下する。DMEの治療も進歩しているが、効果が不十分な症例が存在すること、高額な薬剤の継続使用が必要なケースのあることなどが臨床上の問題になっている。
 糖尿病性腎症に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
糖尿病性腎症に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。一方、DRと同じく糖尿病による細小血管合併症に位置付けられている糖尿病腎症(DN)では、血圧上昇や浮腫が生じやすい。DRやDNはいずれも高血糖が主要なリスク因子だが、DNはそれに伴う高血圧や浮腫という高血糖とは異なる機序によっても、DRやDMEのリスクを押し上げている可能性がある。清澤氏らはこれらの点を、以下のケースシリーズ研究によって検討した。
研究対象は、三島総合病院の眼科を受診した2型糖尿病患者261人(平均年齢70.1±10.1歳、男性54.8%)。このうち127人(48.7%)にDR、64人(24.5%)にDMEが認められた。DMEが認められた患者は全てDRを有していた。
DR群と非DR群を比較すると、年齢、性別、BMI、血清脂質値、および高血圧や虚血性心疾患の有病率には有意差がなかった。一方、DR群の方が糖尿病罹病期間が長く、過去のHbA1cの平均値および最高値が高いという有意差があった。また、推算糸球体濾過量(eGFR)が低く(56.2±26.4対67.1±17.0mL/分/1.73m2)、DNの病期が進行していた(1~5期の病期分類で2.4±1.2対1.4±0.6)。
次に、DRの発症・重症度、およびDMEの発症・重症度という4項目それぞれを目的変数とし、性別、糖尿病罹病期間、BMI、過去のHbA1cの平均値・最高値、血清脂質値、高血圧や虚血性心疾患の既往、およびRAS阻害薬やSGLT2阻害薬の処方を説明変数とする多重回帰分析を施行。その結果、糖尿病の罹病期間が長いことや平均HbA1cとともに、DNの病期がDRおよびDMEの発症と重症度の全てに、それぞれ独立して関連していることが明らかになった。
例えば、DME発症に対して、糖尿病罹病期間はオッズ比(OR)1.33(95%信頼区間1.01~1.75)、平均HbA1cはOR5.52(同1.27~24.1)、DNの病期はOR2.80(同1.37~5.72)だった。性別やBMI、血清脂質値、高血圧や虚血性心疾患の既往、RAS阻害薬やSGLT2阻害薬の処方は、DRおよびDMEの発症や重症度と独立した関連が示されなかった。HbA1c最高値はDRの発症についてのみ、有意な説明因子として抽出された。
このほか、単変量解析からは、eGFRはDRおよびDMEの発症や重症度と有意な負の相関があり、アルブミン尿は有意な正の相関があることが示された。RAS阻害薬やSGLT2阻害薬の処方は、いずれに対しても有意な関連が見られなかった。
以上を基に著者らは、「糖尿病腎症が糖尿病による網膜疾患の発症と進展に関与している可能性が考えられ、腎症の病期は糖尿病網膜疾患の予測因子となり得る」と結論付けている。
糖尿病のセルフチェックに関する詳しい解説はこちら

糖尿病でいちばん恐ろしいのが、全身に現れる様々な合併症。深刻化を食い止め、合併症を発症しないためには、早期発見・早期治療がカギとなります。今回は糖尿病が疑われる症状から、その危険性を簡単にセルフチェックする方法をご紹介します。
-
7月 14 2023 小学生のコロナ感染リスクに近隣の社会経済環境が関連――大阪市での研究
自宅周辺の社会経済環境と、小学生の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)感染リスクとの関連が報告された。高学歴者の多い環境で暮らす小学生は感染リスクが低く、卸売・小売業の従事者が多い環境の小学生は感染リスクが高いという。同志社大学大学院スポーツ健康科学研究科の大石寛氏(大学院生)、同大学スポーツ健康科学部の石井好二郎氏らの研究の結果であり、詳細は「Children」に4月30日掲載された。
居住地域の社会経済環境とCOVID-19感染リスクとの間に有意な関連があることは、既に複数の研究から明らかになっている。ただしそれらの研究の多くは海外で行われたものであり、またCOVID-19重症化リスクの低い小児を対象とした研究は少ない。日本は子どもの相対的貧困率が高いこと、および、当初は低いとされていた子どものCOVID-19感染リスクもウイルスの変異とともにそうでなくなってきたことから、国内の子どもたちを対象とした知見が必要とされる。これを背景として石井氏らは、大阪市内の公立小学校の282校の「学区」を比較の単位とする研究を行った。なお、大阪市内には生活保護受給率が全国平均の3倍を上回る地区が複数存在している。
 COVID-19に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
COVID-19に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。解析には、大阪市内公立小学校のCOVID-19感染患児数、行政機関や民間企業が公表・提供している社会経済環境関連データ、住民の大学卒業者の割合、他者との対面の必要性の高い職業(卸売・小売業、郵便・運輸業、宿泊・飲食業、医療・社会福祉関連業)従事者の割合、地理的剥奪指標(ADI)などのデータを用いた。これら以外に、結果に影響を及ぼす可能性のある共変量として、人口密度、世帯人員、医療機関・高齢者施設の件数、公共交通機関の施設(駅やバス停)の数などを把握した。対象期間は、パンデミック第2~5波に当たる2020年6月~2021年11月。
COVID-19に感染した小学生の数を目的変数、社会経済環境関連の指標を説明変数とし、共変量で調整後の解析で、大学卒業者が多く住んでいる学区では小学生のCOVID-19罹患率が有意に低いという負の相関が認められた〔罹患率比(IRR)0.95(95%信頼区間0.91~0.99)〕。一方、卸売・小売業従事者が多い学区では小学生のCOVID-19罹患率が有意に高いという正の相関が確認された〔IRR1.17(同1.06~1.29)〕。他者との対面の必要性の高いそのほかの職業従事者の割合やADIは、小学生のCOVID-19罹患率との有意な関連がなかった。
パンデミックの波ごとに解析した場合も、自宅近隣に卸売・小売業従事者が多いことは第4・5波で、小学生のCOVID-19罹患率と正の相関が認められた。また、解析対象とした第2~5波の中で最も罹患率の高かった第5波では、医療・社会福祉関連業の従事者が多い学区でも正の相関が見られ〔IRR1.16(1.05~1.28)〕、反対に大学卒業者が多い学区では負の相関が見られた〔IRR0.94(0.90~0.99)〕。このほかに第2波では、宿泊・飲食業の従事者が多い学区で小学生の感染リスクが3倍近く高かったことが分かった〔IRR2.85(1.33~6.43)〕。
以上より著者らは、「自宅近隣の社会経済環境が小学生のCOVID-19感染リスクと関連していることが明らかになった。特に、卸売・小売業従事者が多い地区で罹患率が高く、高学歴者が多い地区は罹患率が低い」とまとめている。また、ADIが有意な関連因子として抽出されなかったことから、「感染防止行動に必要な情報の収集、理解、評価とその実践につながる地域住民の実行力が、社会経済的な格差の有無にかかわらず、その地区の子どもたちのCOVID-19感染リスクを押し下げる可能性がある」と考察。「われわれの研究結果は、COVID-19感染リスクの地域格差を是正するための公衆衛生政策に有用な情報となり得る」と付け加えている。
治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。
HOME>7月 2023