パーキンソン病患者の“よだれ”が示すもの、全身的な神経変性との関連を示唆
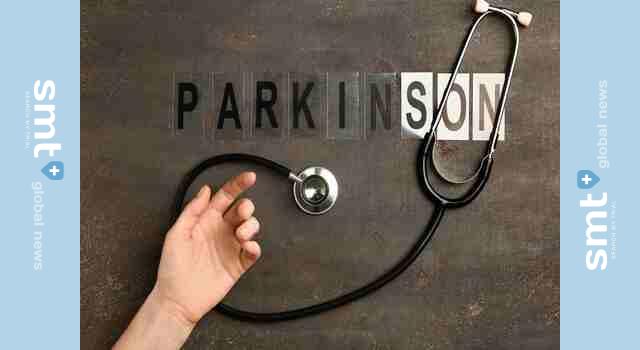
パーキンソン病でよく見られる“よだれ(流涎)”は、単なる口腔のトラブルではないかもしれない。日本の患者を対象とした新たな研究で、重度の流涎がある患者では、運動・非運動症状がより重く、自律神経や認知機能にも異常がみられることが示された。流涎は、全身的な神経変性の進行を映す新たな臨床的サインとなる可能性があるという。研究は順天堂大学医学部脳神経内科の井神枝里子氏、西川典子氏らによるもので、詳細は9月30日付けで「Parkinsonism & Related Disorders」に掲載された。
パーキンソン病は、動作の遅れや震えなどの運動症状に加え、自律神経障害や認知機能低下など多彩な非運動症状を伴う進行性の神経変性疾患である。その中でも流涎(唾液の排出障害)は、生活の質や誤嚥性肺炎リスクに影響するにもかかわらず、軽視されがちで、標準的な評価方法も確立されていない。本研究は、この見過ごされやすい症状の臨床的重要性を明らかにするため、日本のパーキンソン病患者を対象に、流涎の有病率や特徴を調べ、運動・非運動症状との関連を検討することを目的とした。

郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。
本横断研究では、2015年11月~2022年8月の間に順天堂大学医学部附属順天堂医院脳神経内科でパーキンソン病と診断された患者811人を初期スクリーニングした。運動症状および非運動症状は、MDS-UPDRSパートI〜IV、MMSE、MoCA-J、FAB、PDSS-2、JESS、およびPDQ-39を用いて評価した。心臓の自律神経機能は、メタヨードベンジルグアニジン(MIBG)心筋シンチグラフィーによる遅延心・縦隔比(H/M比)で評価した。ドパミン作動性神経の機能は、ドパミントランスポーター単光子放射断層撮影(DaT SPECT)を用い、年齢調整済み基準データベースを基にzスコアを算出した。流涎の重症度は、MDS-UPDRSパートIIの項目2で評価した。群間比較には、連続変数に対してt検定、カテゴリ変数に対してカイ二乗検定を用いた。
本研究の最終的な解析対象は513人で、そのうち341人(66.5%)が流涎症を有しており、144人(28.1%)が重度と診断された。流涎はMDS-UPDRSの全領域(パートI〜IV)で有意に高いスコアと関連し、運動症状・非運動症状のいずれも重症であることを示した(P<0.001〜P=0.011)。流涎群ではMMSE(P=0.010)およびFAB(P=0.006)のスコアが低く、より顕著な認知機能障害を認めた。また、PDSS-2スコアおよびPDQ-39総合スコアはいずれも有意に高値であり(ともにP<0.001)、睡眠の質および生活の質(QoL)の低下が示唆された。さらに、MIBG心筋シンチグラフィー(対象は402例)では心・縦隔比(H/M比)の低下がみられ(P=0.047)、心臓自律神経機能障害の進行が示された。加えて、DaT SPECT(対象は431例)では線条体のzスコアが有意に低下しており(P=0.001)、シナプス前ドパミン作動性神経活動の低下を反映していた。
年齢・罹病期間・性別を調整した多変量回帰解析の結果、流涎の重症度は、より重度の運動症状・非運動症状、高いレボドパ換算用量、より強い認知機能障害、日中過眠の増加、より重度の睡眠障害、生活の質の低下、そしてDaT取り込み量のzスコア低下と有意に関連していた。
著者らは、「流涎を伴うパーキンソン病患者は、運動症状・非運動症状がより重く、認知機能や自律神経機能にも影響がみられ、生活の質も低下していた。これらの結果は、流涎が単独の末梢的症状ではなく、パーキンソン病における全身的な病態進行の臨床マーカーとして機能する可能性があるという仮説を支持するものである」と述べている。
なお、本研究は帝人ファーマ株式会社の支援を受けて実施された。

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。


