糖尿病治療、継続の鍵は「こころのケア」と「生活支援」
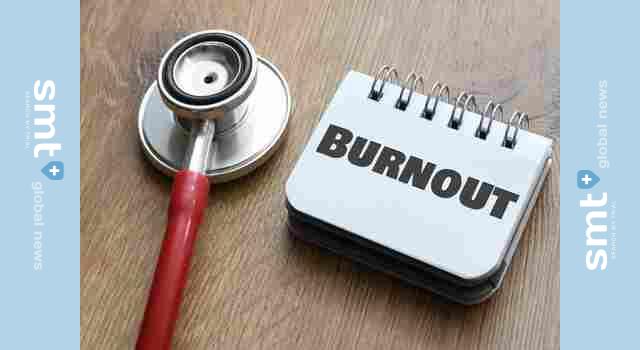
病気の治療を続けたいと思っていても、気持ちの落ち込みや生活の負担が重なると、通院や服薬をやめてしまうことがある。今回、全国の糖尿病患者を対象にした調査で、心理的苦痛や先延ばし傾向がある人ほど治療を中断しやすいことが明らかになった。その背景として、経済的困難や介護・家事の負担、糖尿病治療への燃え尽き症候群(糖尿病バーンアウト)がみられたという。研究は鳥取大学医学部環境予防医学分野の桑原祐樹氏らによるもので、詳細は9月30日付けで「BMJ Open Diabetes and endocrinology」に掲載された。
世界的に糖尿病の有病率は増加しており、合併症による健康への影響が大きな課題となっている。適切な血糖管理により、多くの合併症は予防または遅らせることが可能である。しかし、治療を継続し、医療機関を受診し続けることは容易ではなく、治療中断やアドヒアランスの低下は血糖管理の不良、合併症の進行、死亡リスク、医療コストの増大につながる。過去の研究では、治療継続に関わる心理・社会的要因(抑うつや薬剤費など)が限定的に検討されてきたが、患者の体験と治療中断の関係については十分に解明されていない。本研究は、心理・社会的要因と患者体験が糖尿病治療の中断にどのように関連するかを明らかにすることを目的とした。

郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。
この横断研究では、220万人のパネル会員を持つ楽天リサーチ(現:楽天インサイト)株式会社を通じて、構造化オンラインアンケートを実施した。登録されている糖尿病患者1万8,000人のうち、40〜79歳の1万人を便宜的に抽出した。参加者には「現在、糖尿病の治療を受けていますか?(医療機関での定期的な血液検査や生活指導を含む)」と尋ね、「はい」と答えた者を治療継続群、「いいえ」と回答し、かつ「過去に定期的に治療を受けていたが、現在は医療機関を受診していない」を選択した者を治療中断群に分類した。群分けに続いて、参加者の心理的要因(気分障害・不安障害、自己肯定感、先延ばし傾向)および社会的要因(孤独感、逆境的な幼少期経験:ACE)を測定した。群間の割合の差はカイ二乗検定で評価し、糖尿病治療の中断と心理・社会的要因との関連は、潜在的交絡因子を調整したロジスティック回帰分析で検討した。
適格性を検証後、最終的な解析対象は4,715人(男性86.8%、女性13.2%)となった。69人の参加者が糖尿病治療の中断を報告し、51人が3カ月以上治療を中断していた。
次に、ロジスティック回帰分析により、心理・社会的要因と糖尿病治療中断との関連を検討した。性別、年齢、学歴、世帯収入、糖尿病の型で調整後、心理的苦痛(調整オッズ比〔AOR〕 1.87、95%信頼区間〔CI〕 1.06~3.30、P=0.032)および先延ばし傾向が強いこと(AOR 2.64、95%CI 1.25~5.56、P=0.011)は、治療中断と有意に関連していた。
さらに、治療継続群と治療中断群との患者体験を比較した。全体として、参加者のうち9.7%が経済的困難を訴えていた。また、12.1%が糖尿病バーンアウトを報告していた。経済的困難(9.5%対21.7%、P=0.002)、育児または介護の困難(1.5%対10.0%、P<0.001)、および糖尿病バーンアウト(11.9%対26.7%、P=0.001)を報告した人の割合は、治療継続群に比べて治療中断群で有意に高かった。
著者らは、「潜在的な交絡因子を調整した後も、心理的苦痛および強い先延ばし傾向は治療中断と有意に関連していた。いくつかの心理社会的要因の経験は、治療継続群と比較して治療中断群で有意に多く認められた。医療従事者および医療システムは、糖尿病患者の転帰不良を最小限に抑えるために、これらの要因への対応を優先すべきだ」と述べた。
なお、本研究の限界として、選択バイアスが避けられなかった点、自己申告式の質問票であったため情報バイアスが存在していた可能性がある点などを挙げている。

糖尿病でいちばん恐ろしいのが、全身に現れる様々な合併症。深刻化を食い止め、合併症を発症しないためには、早期発見・早期治療がカギとなります。今回は糖尿病が疑われる症状から、その危険性を簡単にセルフチェックする方法をご紹介します。


