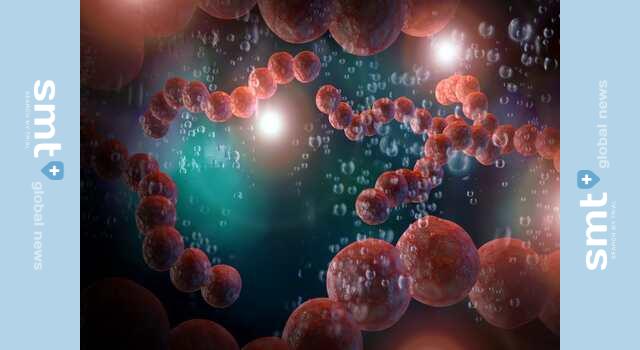-
2月 09 2026 祝日や年末に外傷は増える? 国内データが示す外傷の季節性
救急外来や外傷医療の現場では、患者数の増減が医療提供体制に大きな影響を与える。これまで外傷の発生には季節性があることが知られてきたが、祝日や年末年始といった社会・文化的イベントとの関係を、長期かつ日単位で検証した研究は限られていた。日本全国38万人超の外傷データを解析した本研究では、ゴールデンウィークや年末など特定の時期に外傷が増加する一方で、お盆や年始には減少することが明らかになった。研究は、総合病院土浦協同病院救命救急センター・救急集中治療科の鈴木啓介氏、遠藤彰氏によるもので、詳細は12月18日付で「Scientific Reports」に掲載された。
外傷は世界的に主要な死因・障害原因であり、医療・社会に大きな負担を与えている。外傷発生の季節性や祝日の影響はこれまでにも報告されてきたが、多くは短期間の観察にとどまっていた。比較的均質な文化・行動様式を持つ日本では、ゴールデンウィークやお盆、年末年始など生活リズムが大きく変化する時期が存在し、加えて自殺は春から夏に多いという季節性も知られている。本研究は、18年間にわたる全国外傷データを日単位で解析し、こうした年間を通じた行動パターンと外傷・自殺企図の発生動向を包括的に評価することで、医療資源配分や予防戦略の最適化に資する知見を得ることを目的とした。
 【治験について相談したい方へ】
【治験について相談したい方へ】
治験情報の探し方から参加検討まで、専門スタッフが一緒にサポートします本研究では、2004年1月から2021年12月までの日本外傷データバンク(JTDB)を用いて後ろ向き解析を行った。JTDBは、少なくとも1部位で簡易傷害度スケール(AIS)3以上を有する重症外傷患者のみを登録対象とする全国データベースである。JTDBからは、年齢、性別、受傷日および受傷機転、外傷分類、外傷重症度スコア(ISS)、AIS、退院時転帰などの変数を抽出し、受傷日(年月日)が特定可能な外傷患者を対象とした。対象患者は搬送日ごとに分類し、1年365日それぞれの日単位で解析した。日別の患者数、外傷重症度、自殺企図、死亡率を評価し、周期関数を組み込んだ負の二項回帰、外傷重症度で調整したロジスティック回帰、ならびに一般化極端スチューデント化偏差(GESD)検定を用いて外れ値を同定した。
本研究では38万3,473人が解析に含まれた。解析の結果、外傷症例数は年間を通じて大きく変動し、9~12月に多い傾向が示された。ゴールデンウィーク(4月29日~5月5日)や、文化の日(11月3日)、体育の日(現スポーツの日:10月10日)、年末(12月28~29日)にピークがみられた一方、お盆期間(8月中旬)、特に8月15日前後や年始には減少し、最少は3月7日(886例)、次いで1月3日(898例)であった。
自殺企図は21,637例(全体の5.6%)で、5~6月および8月下旬~9月に増加し、10~12月に減少するなど、全外傷とは異なる季節性が認められた。
日別死亡率は平均9.6%で、年間を通じた変動は小さく、明確な季節性や有意な外れ値は認められなかった。また、2004~2021年の全期間を通じて、外傷症例数の季節変動パターンは概ね一貫していた。
著者らは、「日本の外傷症例数は、祝日や季節的な生活習慣に沿った一定の年間変動を示した。自殺企図は独自の季節性を示したが、外傷全体の症例数や死亡率に大きな影響はなかった。本研究は、外傷医療リソースの計画や予防策を検討するうえで、行動や社会的要因を考慮することの重要性を示している」と述べている。
なお、本研究の限界として、重症外傷患者に限定した解析であり、日本特有の文化的背景を反映している点や、後ろ向き研究のため、祝日と外傷発生の因果関係を直接示せない点などを挙げている。
治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。
-
11月 17 2025 ハンズフリーでも油断禁物、会話が運転中の目の動きを妨げる
道路交通法上、運転中のハンズフリー通話に問題はないが、脳には一定の負荷がかかる可能性があるようだ。最新の研究で、健常成人に眼球運動課題を行ってもらったところ、話しながら課題を行った場合に反応開始時間や眼球移動時間に遅れが生じる傾向があることがわかった。研究は、藤田医科大学病院リハビリテーション部の鈴木卓弥氏、藤田医科大学保健衛生学部リハビリテーション学科の鈴木孝治氏(現所属:金城大学医療健康学部作業療法学科)、上原信太郎氏によるもので、詳細は10月6日付けで「PLOS One」に掲載された。
注意の分散は運動行動に影響を与え、正確な動作や協調が必要なタスクで遅れや誤差を生じることが知られている。特に運転中の通話は、手に持つかハンズフリーかに関わらず周囲の視覚情報への反応を遅らせ、事故リスクを高めることが報告されている。これは、会話による認知的負荷が運転に必要な注意資源(attentional resources)を奪い合うためと考えられる。運転には眼球運動、物体認識、動作の準備、実行といった視覚運動処理が必要であり、会話はこれら、特に周辺視野への眼球運動に干渉する可能性がある。本研究では、健常成人に中心から周辺への眼球運動課題を実施し、会話をする、音声クリップを聞く、課題のみの3つの条件で比較し、会話による眼球運動の反応遅延を検討した。
 治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。本研究では、2019年7月11日から2020年8月13日の間に合計30人の健常成人が募集された。参加者は、21インチのコンピュータディスプレイの前に座り、画面中央から周辺に現れる8か所のターゲットに対して、できるだけ速く正確に視線を向けてもらう眼球運動課題を行った。目の動きはアイ・トラッカーで精密に記録した。参加者は、眼球運動課題を3つの条件で実施した。会話条件では、WAIS-IIIやオリジナルの質問計45問(「イタリアの首都はどこですか?」や「昨日の夜は何時に寝ましたか?」など)に答える形式をとった。聴覚条件では、夏目漱石の小説「吾輩は猫である」の朗読音声を聞き、その内容の理解に集中した。対照条件では、眼球運動課題のみを行い、追加の認知的負荷は課さなかった。3つの実験条件が眼球運動に与える影響を調べるため、各運動パラメータについて、条件(会話、聴覚、対照)および方向(8方向)を被験者内要因とした反復測定分散分析(ANOVA RM)を適用した。
3つの実験条件を比較した結果、ターゲットの位置にかかわらず、会話条件では他の条件より反応開始時間が長いことが分かった。事後比較では、会話条件(平均279.7ミリ秒〔ms〕、標準偏差〔SD〕32.8)は、聴覚条件(平均260.4 ms、SD 29.7、P=0.07、効果量〔d〕=0.62)および対照条件(平均261.3 ms、SD 32.8、P=0.09、d=0.56)と比べて、反応時間が長くなる傾向を示した。
視線移動に要する時間についても同様で、会話条件(平均260.1 ms、SD 107.6)は、聴覚条件(平均141.5 ms、SD 58.9、P<0.05、d=1.37)および対照条件(平均160.8 ms、SD 102.1、P<0.05、d=0.95)より有意に長かった。
さらに、視線調整に要する時間も同様の傾向を示し、会話条件(平均1226.5 ms、SD 723.3)は、聴覚条件(平均493.2 ms、SD 361.5、P<0.05、d=1.28)および対照条件(平均548.9 ms、SD 461.2、P<0.05、d=1.12)より有意に延長していた。
著者らは、「本研究では、迅速かつ正確な視線移動と会話を同時に求められる負荷の高い状況において、視線行動の時間的パラメータが遅れることを示した。これらの結果は、会話に伴う認知的負荷が、視覚運動処理の最初のステップである視線行動の開始や制御に関わる神経プロセスに影響を与える可能性を示唆している」と述べている。
なお、本研究の限界点として、個人ごとの認知負荷を定量化できず、会話そのものか負荷の影響かの区別もつかないため、干渉の閾値や程度は明らかでない点を挙げており、今後の取り組むべき研究課題であるとした。
治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。
-
10月 14 2025 歯みがきで命を守る?手術2週間前の口腔ケアが肺炎予防に効果
高齢患者や基礎疾患を持つ患者においては、術後肺炎をはじめとする感染症対策が周術期管理上の大きな課題となる。今回、愛媛大学医学部附属病院の大規模後ろ向き解析で、術前2週間以上前からの体系的な口腔ケアが術後肺炎の発症抑制および入院期間短縮に有効であることが示された。研究は愛媛大学医学部附属病院総合診療サポートセンターの古田久美子氏、廣岡昌史氏らによるもので、詳細は9月3日付けで「PLOS One」に掲載された。
近年、周術期管理や麻酔技術の進歩により、高齢者や重篤な基礎疾患を持つ患者でも侵襲的手術が可能となった。その一方で、合併症管理や入院期間の短縮は依然として課題である。術後合併症の中でも肺炎は死亡率や医療費増大と関連し、特に重要視される。口腔ケアは臨床で広く行われ、病原菌抑制を通じて全身感染症の予防にも有効とされる。しかし、既存研究は対象集団が限られ、最適な開始時期は明確でない。このような背景を踏まえ、著者らは術前口腔ケアについて、感染源除去や細菌管理、歯の脱落防止のために少なくとも2週間の実施が必要であると仮説を立てた。そして、手術2週間以上前からの口腔ケアが術後肺炎予防に有効かを検証した。
 肺炎に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
肺炎に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。本研究では、2019年4月~2023年3月の間に愛媛大学医学部附属病院で手術および術後管理を受けた成人患者1,806人を対象とした。患者は口腔ケア介入の時期に基づき、手術の少なくとも2週間前に体系的な口腔ケアを受けた群(早期介入群)と、手術の2週間以内に口腔ケアを受けた、もしくは口腔ケアを受けなかった群(後期介入群)の2群に分類した。主要評価項目は、院内感染症のDPCコードを用いて特定された術後感染症(術後肺炎、誤嚥性肺炎、手術部位感染症、敗血症など)の発生率とした。副次評価項目は術後入院期間および入院費用であった。選択バイアスを最小化するために、傾向スコアマッチング(PSM)および逆確率重み付け(IPTW)が用いられた。
解析対象1,806人のうち、257人が早期介入群、1,549人が後期介入群だった。年齢、性別、手術の種類など14の共変量を用いたPSMの結果、253組のマッチペアが特定された。PSMおよびIPTW解析の結果、早期介入群では、後期介入群に比べて術後肺炎の発生率が有意に低いことが示された(PSM解析:リスク差 −5.08%、95%CI −8.19~−1.97%、P=0.001;IPTW解析:リスク差 −3.61%、95%CI −4.53~−2.68%、P<0.001)。
さらに、IPTW解析では早期介入群の入院期間は後期介入群より短く、平均で2.55日短縮されていた(95%CI −4.66~−0.45日、P=0.018)。医療費に関しても早期介入群で平均5,385円の減少が認められた(95%CI -10,445~-325円、P=0.037)。PSM解析では同様の傾向が認められたものの、統計的に有意ではなかった。
著者らは、「本研究の結果は、手術の少なくとも2週間前から体系的な術前口腔ケアを実施することで、術後肺炎の発症を有意に減少させ、入院期間を短縮できることを示している。さまざまな統計解析手法でも一貫した結果が得られたことから、標準化された術前口腔ケアプロトコルの導入は、手術成績の改善に有用な戦略となり得る」と述べている。
本研究の限界については、測定されていない交絡因子が存在する可能性があること、単一の施設で実施されたため、研究結果の一般化には限界があることなどを挙げている。
治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。
-
10月 06 2025 ロボット支援直腸がん手術、術後1日目のCRPで合併症予測が可能に
術後合併症や感染症への対応には、早期発見と迅速な対処が求められる。今回、直腸がんに対するロボット支援下直腸手術(RARS)後の合併症リスクが、術後1日目のC反応性蛋白(CRP)値で予測できるとする研究結果が報告された。術後早期のCRP測定が、高リスク患者の見極めや迅速な介入に役立つ可能性があるという。研究は国立病院機構福山医療センター消化器・一般外科の寺石文則氏らによるもので、詳細は8月28日付けで「Updates in Surgery」に掲載された。
RARSは、骨盤内の限られた視野で高い操作性を発揮し、従来の腹腔鏡手術や開腹手術と同等かそれ以上の成績を示すことが報告されている。しかし、依然として術後合併症は患者予後を左右する大きな課題であり、早期に高リスク患者を見極めることが重要だ。炎症マーカーであるCRPは大腸手術後の合併症予測に有用とされるが、ロボット支援手術における術後早期のCRP値の予測的価値は十分に検討されていない。このような背景を踏まえ著者らは、RARS後の合併症リスク因子を解析し、特に術後1日目のCRP測定の有用性を評価することを目的とした後ろ向きコホート研究を実施した。
 治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。本解析では、岡山大学病院にて、2020年9月から2025年1月にかけて、原発性直腸がんに対して待機的にロボット支援手術を受けた連続症例を対象とした。血清CRP値は、術前および術後1日目と4日目に測定された。主要評価項目は、手術後30日以内に発生したすべての合併症の有無であり、Clavien–Dindo(C–D)分類に基づいて評価した。群間比較は、連続変数についてはt検定またはMann-Whitney U検定、カテゴリ変数についてはカイ二乗検定またはFisherの正確確率検定を用いた。また、単変量解析で有意な因子や臨床的に重要な因子を多変量ロジスティック回帰モデルに投入し、術後1日目のCRPを含む独立した合併症予測因子を特定した。さらに、ROC解析で最適カットオフ値を算出し、Youden指数で評価した。
追跡期間中に直腸がんに対してロボット支援手術を受けた患者117名が本研究の対象となった。平均年齢は66歳で、男性は59.0%を占めた。術後合併症は26名(22.2%)に発生し、腸閉塞(10例)、腹腔内膿瘍および吻合不全(7例)、リンパ漏(2例)などが認められた。手術後30日以内の死亡はなかった。単変量解析により、これらの合併症は高齢、ASAスコア(米国麻酔学会の全身状態評価)の上昇、術前補助療法、ストーマ造設、手術時間の長さ、術後1日目・4日目のCRP値上昇などと有意に関連することが示された。これらの因子を含めた多変量ロジスティック回帰分析を行った結果、術後1日目のCRP値は術後全体の合併症の強力かつ独立した予測因子であることが明らかとなった(調整オッズ比 0.77、95%信頼区間〔CI〕 0.63~0.93、P<0.01)。
5分割交差検証を用いたROC解析では、AUCは0.735(ブートストラップ法によるバイアス補正95%CI 0.544~0.848)であった。術後1日目のCRPの最適カットオフ値は5.63 mg/dLで、この値でYouden指数は最大(0.484)となり、感度 0.615、特異度 0.868を示した。これらの結果から、術後1日目のCRP測定は、直腸がんに対するロボット支援直腸手術後の合併症を予測する有用かつ独立したバイオマーカーであることが示唆された。
本研究について著者らは、「術後1日目のCRP値測定を術後管理に組み込むことで、高リスク患者の早期発見が可能となり、迅速な介入や最終的な手術成績の改善につながる可能性がある」と述べている。
また著者らは、今後の研究において前向きかつ多施設での検証が必要であることを強調するとともに、CRPと他のバイオマーカーを組み合わせることで、予測精度をさらに高められる可能性があることにも言及している。
治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。
-
9月 09 2025 座席位置で変わる生存率、運転席は重症外傷リスクが最大に
自動車の座席位置によって生存率、外傷リスクはどう変わるのか?日本の地域中核病院で20年にわたり収集された交通事故患者のデータを解析した研究により、座席位置が死亡率や外傷の重症度と関連することが示された。特に運転席の乗員は後部座席の乗員に比べて院内死亡や重症外傷のリスクが高かったという。研究は神戸大学大学院医学研究科外科系講座災害・救急医学分野の鵜澤佑氏、大野雄康氏らによるもので、詳細は「BMC Emergency Medicine」に7月30日掲載された。
交通事故は社会に大きな経済的負担を及ぼす公衆衛生上の課題である。世界保健機構(WHO)によると、2023年には約119万人が交通事故で死亡したと報告されている。自動車事故に巻き込まれた負傷者の生存率や転帰を改善するためには、死亡率や解剖学的重症度に影響を与える因子を明らかにすることが極めて重要である。中でも、運転席、助手席、後部座席に分類される座席位置は交通事故による死亡の重要な要因と考えられている。しかしながら、この座席位置と死亡率の関連を検証した先行研究では矛盾する結果も報告されており、依然としてその関係は明確ではない。そのような背景から、著者らは後部座席の位置が死亡率および解剖学的重症度の低下と関連しているという仮説を立て、国内の地域中核病院のデータベースを用いた後ろ向きコホート研究を実施した。
 治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。解析対象は、太田西ノ内病院救命救急センター(福島県郡山市)のデータベースより、2000年から2022年までに四輪自動車乗車中に受傷し、同院に救急搬送された交通事故患者5,906名とした。主要評価項目は院内死亡率とした。その他の評価項目には、重症外傷(外傷重症度総合スコア〔ISS〕が15超と定義)および各部位別(頭頸部、胸部、腹部および骨盤内臓器、四肢および骨盤)の重症外傷(部位別外傷重症度スコア〔AIS〕が3以上と定義)が含まれた。
対象患者5,906人のうち、運転席の乗員は4,104人(69.5%)、助手席は1,009人(17.1%)、後部座席は793人(13.4%)であった。3群間では、年齢、性別、暦年、季節、時間帯、曜日、病院前搬送時間、車種(普通自動車または軽自動車)、受傷機転(衝突の種類や原因)、シートベルトの装着、エアバッグの展開、高エネルギー外傷の有無において有意差が認められた。
多変量ロジスティック回帰モデルを用いて、年齢、性別、暦年、季節、時間帯、曜日、病院前搬送時間、車種、受傷機転、シートベルトの装着、エアバックの展開、高エネルギー外傷などの重要な交絡因子を調整した上で解析した結果、後部座席の乗員は運転席の乗員よりも院内死亡リスクが低いことが明らかになった(調整オッズ比〔AOR〕 0.396、95%信頼区間〔CI〕 0.216~0.727、P<0.025)。
その他の評価項目においても、交絡因子を調整後、後部座席群は運転席群と比較してISS>15の重症外傷リスクが低かった(AOR 0.428、95%CI 0.308~0.596、P<0.025)。特にAIS≧3の胸部(AOR 0.474、95%CI 0.333~0.673、P<0.025)、腹部および骨盤内臓器(AOR 0.373、95%CI 0.218~0.639、P<0.025)において、重症外傷リスクの低下が認められた。
本研究について著者らは、「本研究から、運転席に座る人は死亡や重症外傷のリスクが高く、特別な注意が必要であることが示された。今回の知見は、車に乗る人々だけでなく、救急医療の現場や自動車メーカーにとっても重要な示唆を与えている」と述べている。
なお、サブ解析において後部座席乗員の院内死亡に特有の因子を検討したところ、シートベルトの不適切な着用が院内死亡率の上昇と関連していた(P=0.024)。一方で、後部座席でシートベルトを適切に着用していた乗員に死亡例は認められなかったことから、著者らは後部座席乗員に対してもシートベルト着用を徹底するよう教育・啓発していく必要があると指摘している。
治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。
-
9月 03 2025 肺炎リスクから考える、ICU患者の「口腔ケア」
気管挿管後に発症する人工呼吸器関連肺炎(VAP)は、集中治療室(ICU)に入院する患者における主な感染性合併症であり、その発生率は8~28%に上る。今回、ICU患者において口腔ケアを実施することで、口腔内の細菌数が有意に減少することが確認された。また、人工呼吸器の挿管によって、口腔内の細菌叢(マイクロバイオーム)の多様性が低下することも明らかになった。研究は、藤田医科大学医学部七栗歯科の金森大輔氏らによるもので、詳細は「Critical Care」に7月23日掲載された。
米国の研究ではVAPによって、ICU入院患者の死亡率(24~50%)、ICU滞在期間(約6日間延長)、医療費(1件当たり約4万ドル)が増加することが報告されている。したがって、VAPに対しては予防・早期診断・適切な治療が極めて重要とされる。ただし、ICU患者の口腔ケアは、気管チューブの存在や開口制限により困難を伴い、十分に実施されないことも多い。また、従来の研究では「口腔ケアが肺炎リスクを下げる可能性がある」ことは示唆されていたものの、実際にどの程度口腔内の細菌数や微生物の構成が変化するのか、その実態は十分に明らかにされていなかった。そこで本研究では、ICUに入室した気管挿管中の患者を対象に、口腔ケアが口腔内細菌数および細菌叢の多様性に与える影響を検討した。特に、抜管前後での比較や、16S rRNA遺伝子解析による微生物構成の変化に着目することで、VAP予防における口腔ケアの科学的根拠を補強することを目的とした。
 治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。この単群縦断的介入試験には、2023年2月から5月にかけて、藤田医科大学病院のICUに入院し、48時間以上人工呼吸器を装着したうえで、期間中に抜管された15名の患者が含まれた。口腔内細菌叢のサンプルは、舌表面をスワブで擦過することで採取した。口腔内細菌数の計測は、挿管中の口腔ケアの前後および抜管後の口腔ケアの前後の、計4回にわたって実施された。細菌叢の解析は、挿管中の口腔ケア前および抜管後の口腔ケア前の2時点で行われ、16S rRNA遺伝子アンプリコンシーケンスを用いて実施された。
口腔ケア前の細菌数は、挿管中の方が抜管後よりも有意に多かった(P=0.009)。口腔ケアの介入により、挿管中(P<0.001)および抜管後(P=0.011)のいずれにおいても、口腔内の細菌数は有意に減少した。
次に抜管前後の口腔内細菌叢の多様性を比較した。α多様性(1サンプル内の菌種の豊かさ)の指標である、Shannon指数およびChao1は、挿管中の方が抜管後よりも有意に高かった(それぞれP=0.0479およびP=0.0054)。一方でβ多様性(サンプル間の菌種の豊かさ)については、両時点間で有意な差は認められなかった(P=0.68)。
また、抜管前後における細菌群の変化を明らかにするため、群間比較解析(LEfSe)を実施した。その結果、抜管後には以下の7種の細菌群(Streptococcus sinensis、Prevotella pallens、Saccharimonas sp.〔CP007496_s〕、Campylobacter concisus、Eubacterium brachy、Eubacterium infirmum、Selenomonas sputigena)で有意な減少が認められた。これにより、気管挿管中は口腔内細菌叢のバランスが乱れ、抜管後に回復している可能性が示唆された。
本研究について著者らは、「本研究は、ICU患者において、抜管前後の両期間で口腔ケアが口腔内細菌数を効果的に減少させることを示した。定量的な減少に加えて、マイクロバイオーム解析により、抜管に伴う口腔内細菌叢の組成変化も明らかになり、気管挿管が細菌数だけでなく微生物コミュニティの構造にも影響を与えることが示唆された。これらの結果は、口腔ケアが細菌叢のバランス維持やディスバイオーシス(微生物の乱れ)の予防に重要であり、VAPなどの合併症の予防にも寄与する可能性があることを示しているが、この可能性を確定するにはさらなる研究が必要である」と述べている。
治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。
-
8月 18 2025 男性部下の育休に対する上司の怒り、背景に職場の不公平感とストレス
男性が育児休業(育休)を取りにくい職場の空気はどこから生まれるのか。今回、男性の育休に対する上司の怒りは、業務負担や部下に対する責任感といった職場ストレスが原因となり、不公平感を介して生じている可能性があるとする研究結果が報告された。研究は筑波大学人間系の尾野裕美氏によるもので、詳細は「BMC Psychology」に7月1日掲載された。
日本では男性の育児休業制度は国際的にみても手厚く整備されており、法的には長期間の取得が可能で、一定の所得補償も用意されている。しかし現実には、男性の育休取得率やその取得期間は依然として低く、制度が十分に活用されているとは言いがたい。従来の研究では、育休取得によるワークライフバランスの向上や仕事満足度の向上といった肯定的側面に主に焦点が当てられてきた。一方で、制度活用が職場内で生じさせる不公平感や、上司が感じる感情的な負担といった側面には、これまで十分な検討がなされてこなかった。そこで本研究では、男性部下の長期育休取得に対する上司の否定的感情が、職場におけるストレッサー(不明確な役割や能力を超えた業務など)を通じてどのように形成されるのかを明らかにすることを目的とした。不公平感が怒りの媒介要因となるという仮説モデルに基づき、その相互関係を検証するためのオンライン調査を実施した。
 治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。2024年3月にインターネット調査会社を通じて、30~60歳の民間企業の管理職400名(男女各200名)からデータを収集した。質問項目は、男性育休への怒り、男性の育休に関する不公平感喚起状況(育児関与の希薄さ、手厚い恩恵の享受、自身の仕事量の増加)、職場のストレッサー(質的負荷、量的負荷、部下に対する責任)、属性情報(性別、年齢、職業など)で構成された。
性別と子の有無を要因とする二元配置分散分析を行った結果、「育児関与の希薄さ」「手厚い恩恵の享受」において性別の主効果が有意で、女性の得点が高かった。一方、怒りと不公平感喚起状況との交互作用は認められなかった。職場ストレッサーでは「部下への責任感」にのみ有意な交互作用が認められた。単純主効果検定により、子どものいない男女間では男性が有意に高く、また女性では子ありの方が有意に高かった。一方、「質的負荷」「量的負荷」には交互作用・主効果ともに認められなかった。怒りは、男性育休に関する「育児関与の希薄さ」「手厚い恩恵の享受」「自身の業務負担の増加」の3つの不公平感要因および職場ストレッサーと正の相関を示し、不公平感要因は職場の様々なストレッサーとも関連した。
次に共分散構造分析により、職場のストレスが不公平感を介して上司の怒りに至る理論モデルを検証した。質的・量的負担や部下への責任感が、「育児関与の希薄さ」「手厚い恩恵の享受」「自身の仕事量の増加」といった男性育休に関する不公平感を高め、これらのうち「育児関与の希薄さ」「自身の仕事量の増加」が怒りと有意に関連した。また、量的負担は怒りに直接影響し、責任感は怒りを抑制する効果を示した。モデルの適合度指標はいずれも良好で、仮説モデルの妥当性が確認された。
本研究について著者は、「職場のストレスにより、男性社員の育休取得に対して上司が不公平だと感じ、それが怒りにつながることがある。ワークライフバランス施策には、意図しない負の影響が生じる場合もあり、本研究は、男性の育休に対する職場の反応がどのように職場環境に左右されるかを示すことで、職場の公平性に関する理解を深める手がかりとなる」と述べている。
治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。
-
8月 04 2025 硬膜外カテーテル、13%で位置ずれ? 経験豊富な医師でも注意が必要
硬膜外麻酔時のカテーテル挿入には、高い技量と経験が要求される。しかし、今回、熟練の麻酔科によるカテーテル挿入でも、その先端が適切な位置に届いていないとする研究結果が報告された。カテーテル先端の位置異常が見られた症例では、担当麻酔科の経験年数が有意に長かったという。研究は富山大学医学部麻酔科学講座の松尾光浩氏らによるもので、詳細は「PLOS One」に6月26日掲載された。
硬膜外麻酔は高度な技術を要し、経験豊富な麻酔科医でも約3割の症例で鎮痛が不十分となる。成功率向上の鍵となるのがカテーテル先端の正確な挿入位置だが、その実際の到達部位を客観的に評価した報告は乏しい。本研究では、術後CT画像を用いてカテーテル先端の位置不良の頻度を明らかにするとともに、術者や患者の特性との関連を後ろ向きに検討した。
 治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。解析対象は、2005年1月1日~2022年12月31日までの間に、富山大学附属病院にて硬膜外麻酔を伴う全身麻酔が施行された1万1,559人とした。これらの患者のうち、手術当日を含む術後5日以内に胸部CTまたは腹部CTが撮影された患者を特定した。術後CT画像より、カテーテル先端が黄色靭帯を貫通していなかった場合を「位置異常」と定義した。群間比較にはχ²検定とMann-Whitney U検定を用い、カテーテル位置異常を従属変数、麻酔科医の卒後年数を独立変数としてロジスティック回帰分析を行った。
最終的な解析対象は、術後の胸部または腹部CT画像で硬膜外カテーテルの挿入が確認された189人であった。患者の年齢中央値は71歳(範囲:15~89歳)、女性は全体の41%を占めた。すべての患者において、硬膜外カテーテルは左側臥位で傍正中アプローチにより挿入され、主な挿入部位は胸椎中部(48%)および胸椎下部(49%)であった。挿入を担当した医師の卒後経験年数の中央値は5.7年(2.0~35.4年)であった。
硬膜外カテーテルの位置異常は24人で認められた(12.7%、95%信頼区間〔CI〕8.3~18.3)。これらの症例では、カテーテルの先端は椎骨(椎弓:9、肋横突起:2、棘突起:1)、浅層軟部組織(脊柱起立筋内:5、皮下:4)、深層軟部組織(椎間孔内:2、背側胸膜下腔:1)に確認された。
正常なカテーテル位置群と位置異常群での特性の違いを調べたところ、患者の年齢やBMI、挿入部位による相違は認められなかったが、位置異常群の麻酔科医は卒後の経験年数が有意に長かった(中央値5.6年 vs. 10.1年、P=0.010)。ロジスティック回帰分析を用いて、カテーテルの位置異常と経験年数の相関を解析した結果、カテーテルの位置異常の発生率は麻酔科医の経験年数の増加に伴い有意に増加することが示された(卒後1年あたりのオッズ比1.08、95%CI 1.02~1.15)。
本研究について著者らは、「術後CTで確認された硬膜外カテーテル先端の位置不良は全体の約13%に認められた。挿入を担当した麻酔科医の卒後年数が長いほど位置異常のリスクが高くなる傾向があり、経験豊富な医師であっても適切な挿入位置の確認が重要である」と述べている。
なお、経験年数の増加に伴い、カテーテルの位置異常の発生率が上昇する理由としては、1)経験に伴う不注意や過信による一次的な位置異常、2)経験を積んだ麻酔科医が皮膚へのカテーテル固定に十分な注意を払わなくなり、結果として患者の体動により生じる二次的な位置異常、の2つの可能性が指摘されている。
治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。
-
7月 28 2025 出所受刑者の再犯率と一般市民の認識に乖離
法務省では、広く国民に再犯防止についての関心と理解を深めてもらうため、毎年7月を「再犯防止啓発月間」として定めている。再犯の背景には孤立・貧困・障害・高齢・依存症などの「生きづらさ」があることが多いとされる。新たな被害者を生まないためにも社会全体での理解と支援が不可欠とされているところ、今回、日本人の一般市民の認識と実際の再犯率との間に大きな乖離があるとする研究結果が報告された。この乖離は、性犯罪、強盗、薬物犯罪で顕著だったという。研究はお茶の水女子大学コンピテンシー育成開発研究所/生活科学部心理学科の高橋哲氏によるもので、詳細は「International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology」に6月20日掲載された。
法務省は、刑務所を出所した受刑者が一定期間内に再び犯罪を犯し再収監された割合(再入率)で再犯を集計している。2019年に刑期を終えて出所した約2万人の元受刑者の追跡調査では、5年以内の再入率は34.1%だった。2022年に出所した元受刑者では、2年以内の再入率は男性13.2%、女性10.8%で、高齢者ほど高い傾向が見られた。犯罪を行った者の社会復帰には地域住民の支援が不可欠であるが、誤った認識が更生支援に悪影響を与えることがある。再犯率を過大評価すれば厳罰化が進み、かえって更生を妨げる可能性がある。一方、過小評価は安全対策の欠如を招きかねない。こうした背景から高橋氏は、日本において一般市民が推定する再犯率の値と公式統計の値の乖離を明らかにするため、ウェブ調査を実施した。
 治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。オンライン調査会社によって実施された本調査は、登録モニターから男女200人ずつ計400人を,20~60歳代の年齢層別に均等になるよう抽出し実施された。また、質問に対して十分な注意を払っていない回答者を除外するための設問も含まれていた。調査では、参加者に7種の犯罪(殺人、強盗、放火、覚せい剤取締法違反〔薬物犯罪〕、強制性交・強制わいせつ致傷〔性犯罪〕、傷害・暴行〔暴力犯罪〕、窃盗〔財産犯罪〕)および犯罪全般の再犯率を推定させた。その際、犯罪白書の再入率の定義と同一になるよう平易に書き下し、公式統計の定義に則り、再犯は必ずしも同一罪名に限定されるものではなく、また、未遂事案も含まれることを明示して回答を求めた。推定再犯率は性別・年齢層別に算出され、令和5年版『犯罪白書』(法務省、2023)の出所受刑者の5年以内再入率の値と比較された。推定値は平均と95%信頼区間(CI)で示され、CIに公式値が含まれない場合は「乖離している」と判断した。
最終的に381人(平均年齢44.85±13.83歳)から有効な回答を得た。性別ごとの調査結果では、男女ともに7種類の犯罪すべてにおいて参加者の推定再犯率が公式統計を上回った。特に性犯罪、強盗、薬物犯罪で乖離が顕著で、それぞれ27.35、23.11、18.54パーセントポイントの差が認められた(全体集団との比較)。年齢層別に見ると、40代・50代の推定再犯率は全般的に公式統計を上回った。特に50代における性犯罪の推定再犯率が54.62%と高く、公式統計の21.0%と比べて33.64パーセントポイントの大きな乖離が認められた。
性別および年齢層を独立変数とする二要因分散分析の結果、いずれの犯罪においても、推定再犯率に性別による有意な影響は認められなかった。一方、年齢層は薬物犯罪の推定再犯率に有意な影響を与えていた(F〔4,371〕=3.13、P=0.015、η²=0.033)。事後検定の結果、40代の推定再犯率は20代と比較して有意に高いことが明らかになった。
また、分散分析の結果、放火、暴力犯罪、財産犯罪の推定再犯率には、性別と年齢の交互作用が認められた。特に40代男性は、同年代の女性や30代男性と比べて、放火の再犯率を高く見積もる傾向があった。暴力犯罪や財産犯罪においても、40代男性は同年代の女性や20代男性より再犯率を高く見積もる傾向があり、複数の犯罪にわたって再犯率を過大評価する傾向が40代男性に認められた。
本研究について高橋氏は、「本研究は、日本においても犯罪種別を問わず再犯率が過大推定される傾向があることを示した。特に性犯罪での過大推定が顕著で、中年男性が特定犯罪の再犯率を高く見積もる傾向があった。欧米の先行研究は再犯の定義が不明確であったり、比較対象となる公式統計が全国的には整備されていなかったりするなど方法論上の不備があるところ、本研究はそれらの結果を補うものであり、また、日本の文化的特徴を踏まえた貴重な知見を提供していると考える。元受刑者の円滑な社会復帰を促進させるためには、こうした認識のギャップを解消するためのさらなる研究が必要である」と述べている。
治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。
-
7月 07 2025 産婦人科医が授業に、中学生の性知識が向上か
インターネットは、性に関する知識を求める若者にとって主要な情報源となっているが、オンライン上には誤情報や有害なコンテンツが存在することも否定できない。このような背景から、学校で行われる性教育の重要性が高まっている。今回、婦人科医による性教育が、日本の中学生の性に関する知識と意識の大幅な向上につながる、とする研究結果が報告された。ほとんどの学生が産婦人科医による講義を肯定的に評価していたという。研究は、日本医科大学付属病院女性診療科・産科の豊島将文氏らによるもので、詳細は「BMC Public Health」に5月28日掲載された。
インターネットへのアクセスが容易になり、子どもたちの性的な内容への露出に対する懸念が高まったことにより、多くの国々が国際的なガイドラインを導入し、包括的な性教育(CSE)プログラムを推進するようになった。2000年には、汎米保健機構(PAHO)と性の健康世界学会(WAS)は、世界保健機構(WHO)と共同で「セクシュアル・ヘルスの推進 行動のための提言」を作成し、全ての人にCSEを提供することを提案した。
 治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。日本でも、この提言に呼応し、適切な性に関する知識を得るためのCSEプログラムが求められている。また、世界的に多くのCSEプログラムでは、ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン接種が重要な要素として含まれている。これは、HPVと子宮頸がんとの関連が確立されており、子宮頸がんは「予防可能」であることに由来する。このような背景を踏まえ著者らは、専門医による性教育の講義が、日本の中学生の経口避妊薬(OC)、避妊、子宮頸がん、HPVワクチン接種に関する知識と意識に与える影響を評価することとした。授業の前後にアンケート調査を実施し、知識と意識の変化を調査した。
本研究では、日本国内の公立および私立の中学校37校に通う中学3年生の男女を対象とした。講義で取り上げたトピックは、文部科学省のCSEガイドラインに従い、1:男女の体の違い、2:月経の問題とその管理、3:避妊方法、4:LGBTQやデートDVに関する問題、5:性感染症、6:子宮頸がんとHPVワクチン、の6つとした。生徒は講義の前後にアンケートに回答し、講義内容に関する知識と意識を評価された。
事前アンケートには5,833名、事後アンケートには5,383名が回答し、男女比はほぼ均等だった。講義に先立ち実施した事前アンケートでは、性に関する情報源と現状の知識について回答を得た。情報源として「インターネットやYouTube」と回答した生徒の割合が最も多かったが、男女別に見ると男子学生の割合が有意に高かった。女子学生は「学校の先生や授業」や「両親・家族」を情報源として挙げる割合が高かったのに対し、男子学生では、「友人」や「この種の情報を得たことがない」と回答する割合が高かった。また、講義前はOC、子宮頸がん、HPVに関する知識が乏しく、多くの学生がHPVワクチンに対して不安を抱いていた。
講義後、OCに関する知識(使用可能年齢や副作用など)が向上し、生理痛の緩和など避妊以外のメリットを認識する学生が増えた。また、避妊方法の理解も著しく深まり、「避妊は男性が責任を持つべき」と考える学生の数は減少した。さらに、子宮頸がんやHPVに関する知識も大幅に向上し、HPVワクチンの接種を希望する学生の割合も増加した。
講義後に実施したアンケートでは、ほとんどの学生が今回の講義を肯定的に評価し、5段階評価で4または5を選択した。男子学生よりも女子学生の方が、わずかに高い評価をしていた。
本研究について著者らは「本研究は、国際機関や先行研究の提言を踏まえ、日本の若者にとって包括的でアクセスしやすい性教育の必要性を明確にした。婦人科医などの専門医が関与することで、性に関する幅広い健康トピックについて正確かつ最新の情報を提供でき、こうした介入の効果をさらに高めることができるだろう」と述べている。
治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。
HOME>ニュース