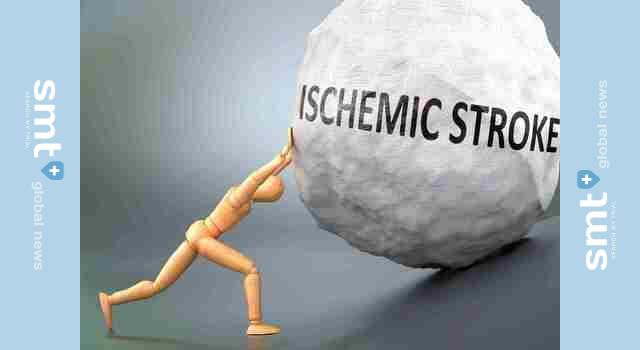-
10月 27 2025 肝疾患患者の「フレイル」、独立した予後因子としての意義
慢性肝疾患(CLD)は、肝炎ウイルス感染や脂肪肝、アルコール性肝障害などが原因で肝機能が徐々に低下する疾患で、進行すると肝硬変や肝不全に至るリスクがある。今回、こうした患者におけるフレイルの臨床的意義を検討した日本の多機関共同後ろ向き観察研究で、フレイルが独立した予後不良因子であることが示された。研究は、岐阜大学医学部附属病院消化器内科の宇野女慎二氏、三輪貴生氏らによるもので、詳細は9月20日付けで「Hepatology Reseach」に掲載された。
CLDは進行すると予後不良となることが多く、非代償性肝硬変患者では5年生存率が約45%と報告されている。このため、将来的な疾患進行や合併症のリスクを減らすには、高リスク患者の早期特定が重要である。一方、最近の研究では、フレイルもCLD患者の予後に影響する独立因子であることが示されており、肝機能だけでなく身体全体の脆弱性を考慮した評価の重要性が指摘されている。Clinical Frailty Scale(CFS)は2005年に開発され、米国肝臓学会もCLD患者のフレイル同定に推奨する評価ツールであるが、これまで日本人CLD患者においてCFSを用いた評価は行われておらず、その臨床的意義は明らかでなかった。こうした背景から、著者らはCFSを用いて日本人CLD患者のフレイルの有病率、臨床的特徴、ならびに予後への影響を明らかにすることを目的とした。
 慢性肝疾患に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
慢性肝疾患に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。本研究では、2004年3月~2023年12月の間に岐阜大学医学部附属病院、中濃厚生病院、名古屋セントラル病院に入院した成人CLD患者とした。CFSスコアは、入院当日の情報に基づき、併存疾患、日常生活動作、転倒リスクに関する質問票を後ろ向きに評価し、スコアが5以上(CFS 5~9)の場合をフレイルと定義した。本研究の主要評価項目は全死亡とした。群間比較には、カテゴリ変数に対してはカイ二乗検定、連続変数に対してはマン・ホイットニーU検定を用いた。生存曲線はカプラン–マイヤー法で推定し、群間差はログランク検定で比較した。フレイルが死亡に与える予後影響はCox比例ハザードモデルで評価し、結果はハザード比(HR)と95%信頼区間(CI)で示した。フレイルと関連する因子は多変量ロジスティック回帰モデルで解析した。
最終的に、本研究には715人のCLD患者(中央値年齢67歳、男性49.5%)が含まれた。最も多かった病因はウイルス性(38.7%)であり、続いてアルコール性(22.2%)、代謝機能障害関連(9.5%)であった。Child–Pugh分類およびModel for End-Stage Liver Disease(MELD)スコアの中央値はそれぞれ7と9であり、CFSスコアの中央値は3であった。これらの患者のうち、フレイルは137人(19.2%)に認められた。フレイル患者のCFSスコア中央値は6であり、年齢が高く、BMIが低く、肝予備能も低い傾向にあった。
中央値2.9年の追跡期間中に221人(28.0%)が肝不全などで死亡した。フレイル患者は、非フレイル患者に比べて有意に生存期間が短かった(中央値生存期間:2.4年 vs. 10.6年、P<0.001)。多変量Cox比例ハザード解析の結果、フレイルはCLD患者における独立した予後不良因子であることが示された(HR:1.75、95%CI:1.25~2.45、P=0.001)。
また、フレイルの決定因子に関して、多変量ロジスティック回帰解析をおこなったところ、高齢、肝性脳症、低アルブミン血症、血小板減少、国際標準比(INR)の延長がフレイルと関連していることが示された。さらにフレイルの有病率はChild–Pugh分類の悪化とともに有意に増加し、Child–Pugh A群では4%、B群では22%、C群では55%の患者にフレイルが認められた。
著者らは、「本研究から、CLD患者ではフレイルが高頻度に認められ、独立した予後不良因子としての役割を持つことが示された。予後への影響を考慮すると、CLD患者ではフレイルを日常的に評価し、転帰改善を目的とした介入を検討することが望ましい」と述べている。
治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。
-
10月 27 2025 尿検査+SOFAスコアでCOVID-19重症化リスクを早期判定
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のオミクロン株の多くは軽症だが、重症化する一部の患者をどう見分けるかは医療現場の課題だ。今回、東京都内の病院に入院した842例を解析した研究で、尿中L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)とSOFA(Sequential Organ Failure Assessment score)スコアを組み合わせた事前スクリーニングが、重症化リスク判定の精度を高めることが示された。研究は国立国際医療センター腎臓内科の寺川可那子氏、片桐大輔氏らによるもので、詳細は9月11日付けで「PLOS One」に掲載された。
世界保健機関(WHO)が2020年3月にCOVID-19のパンデミックを宣言して以来、ウイルスは世界中に広がり、変異株も多数出現した。現在はオミクロン株の亜系統が主流となっており、症状は多くが軽症にとどまる一方、一部の患者は酸素投与や入院を必要とし、死亡する例も報告されている。そのため、感染初期の段階で重症化リスクを予測する方法の確立が求められている。
 COVID-19に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
COVID-19に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。著者らは以前、L-FABPの測定がCOVID-19重症化予測に有用であることを示したが、症例数が少なく、他の指標との併用は検討されていなかった。そこで本研究では、COVID-19患者の入院前スクリーニングとして、L-FABP値と血液検査から多臓器の機能障害を評価するSOFAスコアを組み合わせ、重症化リスクのある患者を特定する併用アプローチの有用性を評価した。
本研究は単施設の後ろ向き観察研究で、2020年1月29日から2022年4月6日までに国立国際医療センターに入院したCOVID-19陽性患者842名を対象とした。L-FABP値とSOFAスコアは、入院時および入院7日目に評価した。人工呼吸器管理を要した患者、または入院中に死亡した患者を「重症」と定義し、酸素療法を受けるが人工呼吸器を必要としない患者を「中等症」、それ以外を「軽症」と分類した。主目的は、入院時のL-FABP値から7日目の重症度を予測できるかどうかを評価することである。さらに、入院時のL-FABP値とSOFAスコアの予測性能を検討するため、ROC(受信者動作特性)曲線解析を実施した。
入院時の重症度分類は軽症536名、中等症299名、重症7名であった。入院中に32名が死亡した。入院7日目には、入院時中等症だった55名が軽症に改善する一方で、重症患者は7名から34名に増加した。解析対象患者全員のL-FABP値を入院時と入院7日目の2時点でプロットし、疾患重症度の経過を可視化したところ、入院時にL-FABP値が高かった患者の一部は、軽症から中等症、あるいは中等症から重症へと進行していた。同様に、SOFAスコアでも、入院時にスコアが高かった患者は7日後に重症化する傾向が認められた。
次にROC曲線解析を行い、L-FABP値とSOFAスコアの組み合わせが、重症例および重症・中等症例の識別にどの程度有効かを評価した。L-FABP値はカットオフ値11.9で重症例を特定する感度が94.1%と高く、SOFAスコアの82.4%を上回り、効果的なスクリーニングツールとなる可能性が示された。さらに、L-FABP値(AUC 0.81)とSOFAスコア(AUC 0.90)を組み合わせると、重症例検出のAUCは0.92に上昇した。このAUCの向上は、SOFAスコア単独との比較では統計学的に有意ではなかったが、L-FABP値単独との比較では有意であった(P<0.001)。一方、重症・中等症例の検出においては、L-FABP値(AUC 0.83)とSOFAスコア(AUC 0.83)の組み合わせによりAUCは0.88となり、いずれか単独の指標よりも有意にAUCを向上させた(それぞれP<0.001)。
著者らは、本予測モデルにさらなる検証と改良が必要と指摘しつつ、「まず低侵襲な尿検査でL-FABP値を測定し、低リスクの患者は不要な入院を回避する。次にL-FABP値が高い患者を対象にSOFAスコアで重症化リスクを精査し、入院が必要な患者を特定する。これにより、不要な入院の削減や重症化リスクの早期把握が期待され、医療資源の効率的な配分にもつながる」と述べ、二段階のスクリーニング戦略を提案している。
治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。
-
10月 20 2025 医療用麻薬の量が睡眠の質に関連か、非がん性慢性疼痛患者の新知見
オピオイド鎮痛薬(以下、オピオイド)はその多くが医療用麻薬に指定され、強い鎮痛作用を持つ。今回、がん以外の慢性的な痛みを抱える患者(非がん性慢性疼痛)において、オピオイドの使用量が睡眠の質と関連する可能性が示された。オピオイド未使用と比較して、高用量のオピオイド使用では総睡眠時間が短く、夜中に目が覚める時間が長い傾向がみられた一方、低用量のオピオイド使用では、睡眠の質が良好な傾向がみられたという。順天堂大学医学部麻酔科・ペインクリニック講座の池宮博子氏らによる研究で、詳細は9月8日付けで「Neuropsychopharmacology Reports」に掲載された。
非がん性慢性疼痛の治療においても医療用麻薬が用いられることがあるが、その使用には慎重な判断が求められる。特に、高用量を長期間使用することの有益性は限定的とされ、睡眠への影響についても様々な報告があり、専門家の間でも一定の見解は得られていない。睡眠は生活の質に大きく影響するため、臨床的意義は大きい。このような背景を踏まえ、著者らは非がん性慢性疼痛で強オピオイドを6か月以上の長期にわたり使用している患者の睡眠状態を明らかにするため、比較研究を行った。
 がん性疼痛に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
がん性疼痛に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。本研究では、順天堂大学医学部附属順天堂医院の麻酔科・ペインクリニックを定期受診している慢性の非がん性疼痛患者29人を対象とした。患者はオピオイドの使用状況に基づき、オピオイド未使用群(11人)、弱オピオイド使用群(8人)、強オピオイドを1日モルヒネ換算量60mg未満で使用する群(5人)、および60mg以上で使用する群(5人)の4群に振り分けられた。痛みの強度や不安・抑うつ(HADS)、痛みを悲観的に考える傾向(PCS)、ストレス(JPSS)などの心理状態を質問票で評価した。また、主観的な睡眠状態も質問票であるAISで評価した。そして、総睡眠時間、中途覚醒時間、睡眠効率などの客観的睡眠指標は、ウェアラブル機器を用いて7晩にわたり測定した。睡眠データは、オピオイド未使用群を基準群として線形混合効果モデルで解析した。モデル1は年齢、性別、痛みの強度、測定日で補正し、モデル2ではさらにPCS、HADS、JPSSを加えて補正した。
弱オピオイド使用群の患者は全員トラマドール塩酸塩を使用していた。強オピオイド群で1日60mg未満の患者はフェンタニル貼付剤またはモルヒネ塩酸塩を使用し、1日60mg以上の患者はフェンタニル貼付剤、オキシコドン塩酸塩、またはモルヒネ塩酸塩を使用していた。
解析の結果、モデル1では高用量群で総睡眠時間が短く(平均411 vs. 290分、P<0.001)、中途覚醒時間が長く(平均106 vs. 189分、P<0.01)、睡眠効率が低い(平均79.8 vs. 64.0%、P<0.001)ことが示された。モデル2でも同様の傾向は維持されたが、一部で統計的有意性がみられなかった。一方で、低用量群では、モデル2で中途覚醒時間が短く(平均121.4 vs. 47.6分、P<0.001)、睡眠効率が高い(平均77.1 vs. 88.8%、P<0.001)傾向がみられた。
主観的な不眠症状は、強オピオイド使用群の両群で認められ、とくに高用量群で顕著だった。
本研究について著者らは、「今回の結果は、非がん性慢性疼痛の患者さんで高用量の強オピオイドを使用する場合、睡眠への影響を評価する重要性を示している。一方、強オピオイド低用量群で見られた、睡眠効率が比較的高く、中途覚醒時間が短いという結果は、オピオイドの鎮痛効果と良好な睡眠を両立させるためには、慎重な用量調整が重要である可能性を示唆している」と述べている。
肺がんのセルフチェックに関する詳しい解説はこちら

肺がんは初期の自覚症状が少ないからこそ、セルフチェックで早めにリスクを確かめておくことが大切です。セルフチェックリストを使って、肺がんにかかりやすい環境や生活習慣のチェック、症状のチェックをしていきましょう。
-
10月 20 2025 がんサバイバーに潜む脳卒中リスク、年齢・高血圧・血液検査値がカギ
がんと診断された人(がんサバイバー)は、そうでない人と比較して脳卒中を発症するリスクが高いことが報告されている。今回、大阪大学の大規模研究で、がんサバイバーにおける脳梗塞の発症率とそのリスク因子が明らかになった。年齢以外に血圧や血液の数値といった身近な健康指標が関わっているという。研究は大阪大学医学部4回生の寺田博昭氏、中村賢志氏、同大学大学院医学系研究科神経内科学講座の権泰史氏らによるもので、詳細は9月7日付けで「THROMBOSIS RESEARCH」に掲載された。
がんサバイバーは脳卒中のリスクが高く、治療中断や予後不良につながることが報告されている。一般人口と比べ脳卒中関連死亡は約2倍で、臨床上の大きな課題となっている。既存研究では、がんサバイバーにおけるがん診断後1年以内の脳梗塞累積発症率は0.9~4%程度と報告され、著者らが行った日本の大規模研究でも同様の傾向が示された。脳梗塞発症リスクは男性や進行がん、心房細動、高血圧などで高く、脳転移も一因となる可能性がある。がんサバイバーの予後改善に伴い動脈血栓塞栓症への関心が高まっており、さらなる疫学的データの蓄積が求められている。こうした背景を踏まえ、著者らはがんサバイバーにおける脳梗塞の発症率を調査し、この集団におけるリスク因子を特定することを目的とした、後ろ向きの単施設観察研究を実施した。
 がんに関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
がんに関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。解析対象は、2007年1月1日~2020年12月31日までの間に大阪大学医学部附属病院の院内がん登録に登録されたすべてのがん患者とした。主要評価項目はがん診断後の脳梗塞発症とした。患者は、がん診断時点から1年間追跡され、死亡を競合リスクとして脳梗塞の累積発生率を評価した。リスク因子はFine and Grayの競合リスクモデルを用いて解析し、サブディストリビューションハザード比(SHR)とその95%信頼区間(CI)を算出した。年齢、性別、既往歴、がんの病期に加え、がん患者の血栓症リスク評価に用いられるKhoranaスコアの構成要素(がん種、白血球数、血小板数)も潜在的な交絡因子として考慮した。
最終的な解析対象は3万5,862人(年齢中央値 65歳、男性 50.3%)となった。最も多かったがん種は乳がん(10.3%)であり、ついで子宮がん(9.6%)、大腸がん(8.2%)などであった。追跡期間中、188人の患者が脳卒中を発症した。そのうち最も多かったのは脳梗塞で143人(76.1%)が発症し、次いで脳内出血が38例(20.2%)、くも膜下出血が7例(3.7%)であった。がん診断後1年間の脳梗塞累積発生率は0.42%であった。
次にFine and Grayの競合リスクモデルを用いて脳梗塞発症のリスク因子を分析した。多変量解析では、脳梗塞発症の独立したリスク因子として、高齢(調整後SHR 1.01、95%CI 1.00~1.03)、高血圧(1.59、95%CI 1.10~2.30)、脂質異常症(1.60、95%CI 1.09~2.36)、心房細動(2.42、95%CI 1.54~3.81)、進行がん(1.74、95%CI 1.12~2.70)が同定された。さらに、がん診断時の白血球数(≥11,000/μL:2.36、95%CI 1.35~4.14)および血小板数(≥350,000/μL:2.24、95%CI 1.05~4.79)の上昇も独立した予測因子であった。
本研究について著者らは、「今回の結果は、高齢、⾼血圧、脂質異常症、心房細動、進行がん、ならびに白血球数および血小板数の上昇が、がんサバイバーにおける脳梗塞の潜在的なリスク因子である可能性を示唆している。今後の研究では、増加するこの集団において高リスク者を特定し、脳梗塞発症を予測するツールの開発を目指すべきである」と述べている。
肺がんのセルフチェックに関する詳しい解説はこちら

肺がんは初期の自覚症状が少ないからこそ、セルフチェックで早めにリスクを確かめておくことが大切です。セルフチェックリストを使って、肺がんにかかりやすい環境や生活習慣のチェック、症状のチェックをしていきましょう。
-
10月 14 2025 高齢者のポリドクター研究、最適受診施設数は2〜3件か
複数の医療機関に通う高齢者は多いが、受診する施設数が多ければ多いほど恩恵が増すのだろうか。今回、高齢者を対象とした大規模コホート研究で、複数施設受診が死亡率低下と関連する一方、医療費や入院リスクが上昇することが明らかとなった。不要な入院を予防するという観点からは最適な受診施設数は2〜3件とされ、医療の質と負担を両立させる上での示唆が得られたという。研究は慶應義塾大学医学部総合診療教育センターの安藤崇之氏らによるもので、詳細は9月1日付で「Scientific Reports」に掲載された。
高齢者では、複数の併存疾患を抱える人も少なくない。多疾患は死亡率や要介護、入院率、医療費の増加と関連しており、高齢化社会を特徴とする先進国の医療制度に大きな課題をもたらしている。特に日本では、多疾患を持つ高齢者の増加に伴い、「ポリドクター(polydoctoring、複数の医師による診療)」と呼ばれる現象が社会的な問題となっている。「ポリドクター」は、異なる医師や医療施設が患者を管理することで、ケアの分断や医療費の増加を招くリスクがある点が懸念されている。
 治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。著者らは以前、高齢者のポリドクターの背景として、眼疾患や骨粗鬆症、前立腺疾患、変形性関節症といった慢性疾患が関連することを示した。しかし、ポリドクターが患者の転帰にどのように影響するかは十分に解明されていない。そこで著者らは、日本の大規模保険請求データベースを用い、多疾患を抱える高齢者の定期通院施設数(RVF)と、死亡や入院などの転帰との関連を明らかにするため、後ろ向きコホート研究を実施した。
本研究では、DeSCヘルスケア株式会社が提供するデータベースを用い、75~89歳の複数の慢性疾患を有する患者233万8,965人を解析対象とした。追跡期間は2014年4月~2022年12月であった。主要評価項目は全死亡率とした。副次評価項目は全入院、外来ケアで予防可能な疾患(ACSC)による入院、外来医療費が含まれた。いずれの評価項目も多変量Cox比例ハザードモデルを用いて、補正ハザード比(HR)および95%信頼区間(CI)を算出した。各群の比較はRVFが1施設の群を基準として行った。
解析対象の中央値年齢は78歳で、参加者の58%が女性だった。RVFの中央値は2施設、併存疾患の中央値は5つであった。外来医療費の中央値は37万1,230円だった。追跡期間中に33万8,249人(14.5%)が死亡し、122万201人(52.2%)が入院した。そのうち29万1,376人(12.5%)はACSCによる入院であった。
全死亡に対する多変量Cox比例ハザードモデルでは、RVFが0施設の群(定期受診なし)が最も死亡率が高く、RVFの施設数が増えるにつれて生存率は改善した。RVFが0施設の参加者の死亡リスクは最も高く、ハザード比(HR)は3.23(95%CI 3.14~3.33、P<0.0001)であった。一方、RVFが5施設以上の参加者では死亡リスクが最も低く、HRは0.67(95%CI 0.62~0.73、P<0.0001)であった。ACSCによる入院では、2~3施設の群で入院率が最も低く、RVFが5施設以上になると再び入院率が上昇するU字カーブを描いた。
外来医療費についても、RVFの施設数が増えるにつれて費用も増加する傾向が見られた。RVFが5施設以上の参加者では、RVFが1施設の参加者に比べ外来医療費が3.21倍(95%CI 3.17~3.26、P<0.0001)に増大した。
本研究について著者らは、「ポリドクターは死亡率を低下させる一方で、入院率や医療費の増加とも関連しており、ACSCによる入院を最小化する最適な受診施設数は2~3施設であることが示された。これらの結果は、高齢化社会において、ケアの連携や医療資源の管理を改善しつつ、ポリドクターのメリットとコストのバランスをとる戦略の必要性を示している」と述べている。
なお、RVFが5施設以上になると再び入院率が上昇する理由については、関与する医療機関が多すぎるとケアの継続性が損なわれ、全体的なメリットが減少する可能性を指摘している。
治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。
-
10月 14 2025 歯みがきで命を守る?手術2週間前の口腔ケアが肺炎予防に効果
高齢患者や基礎疾患を持つ患者においては、術後肺炎をはじめとする感染症対策が周術期管理上の大きな課題となる。今回、愛媛大学医学部附属病院の大規模後ろ向き解析で、術前2週間以上前からの体系的な口腔ケアが術後肺炎の発症抑制および入院期間短縮に有効であることが示された。研究は愛媛大学医学部附属病院総合診療サポートセンターの古田久美子氏、廣岡昌史氏らによるもので、詳細は9月3日付けで「PLOS One」に掲載された。
近年、周術期管理や麻酔技術の進歩により、高齢者や重篤な基礎疾患を持つ患者でも侵襲的手術が可能となった。その一方で、合併症管理や入院期間の短縮は依然として課題である。術後合併症の中でも肺炎は死亡率や医療費増大と関連し、特に重要視される。口腔ケアは臨床で広く行われ、病原菌抑制を通じて全身感染症の予防にも有効とされる。しかし、既存研究は対象集団が限られ、最適な開始時期は明確でない。このような背景を踏まえ、著者らは術前口腔ケアについて、感染源除去や細菌管理、歯の脱落防止のために少なくとも2週間の実施が必要であると仮説を立てた。そして、手術2週間以上前からの口腔ケアが術後肺炎予防に有効かを検証した。
 肺炎に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
肺炎に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。本研究では、2019年4月~2023年3月の間に愛媛大学医学部附属病院で手術および術後管理を受けた成人患者1,806人を対象とした。患者は口腔ケア介入の時期に基づき、手術の少なくとも2週間前に体系的な口腔ケアを受けた群(早期介入群)と、手術の2週間以内に口腔ケアを受けた、もしくは口腔ケアを受けなかった群(後期介入群)の2群に分類した。主要評価項目は、院内感染症のDPCコードを用いて特定された術後感染症(術後肺炎、誤嚥性肺炎、手術部位感染症、敗血症など)の発生率とした。副次評価項目は術後入院期間および入院費用であった。選択バイアスを最小化するために、傾向スコアマッチング(PSM)および逆確率重み付け(IPTW)が用いられた。
解析対象1,806人のうち、257人が早期介入群、1,549人が後期介入群だった。年齢、性別、手術の種類など14の共変量を用いたPSMの結果、253組のマッチペアが特定された。PSMおよびIPTW解析の結果、早期介入群では、後期介入群に比べて術後肺炎の発生率が有意に低いことが示された(PSM解析:リスク差 −5.08%、95%CI −8.19~−1.97%、P=0.001;IPTW解析:リスク差 −3.61%、95%CI −4.53~−2.68%、P<0.001)。
さらに、IPTW解析では早期介入群の入院期間は後期介入群より短く、平均で2.55日短縮されていた(95%CI −4.66~−0.45日、P=0.018)。医療費に関しても早期介入群で平均5,385円の減少が認められた(95%CI -10,445~-325円、P=0.037)。PSM解析では同様の傾向が認められたものの、統計的に有意ではなかった。
著者らは、「本研究の結果は、手術の少なくとも2週間前から体系的な術前口腔ケアを実施することで、術後肺炎の発症を有意に減少させ、入院期間を短縮できることを示している。さまざまな統計解析手法でも一貫した結果が得られたことから、標準化された術前口腔ケアプロトコルの導入は、手術成績の改善に有用な戦略となり得る」と述べている。
本研究の限界については、測定されていない交絡因子が存在する可能性があること、単一の施設で実施されたため、研究結果の一般化には限界があることなどを挙げている。
治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。
-
10月 06 2025 ビタミンD欠乏症が10年間で有意に減少、骨折リスク低減に期待
骨や筋肉の健康を守るうえで欠かせない栄養素、ビタミンD。その不足は骨粗鬆症や骨折リスクの増大と関わることが知られている。今回、日本の大規模調査で、一般住民におけるビタミンD欠乏の割合がこの10年で有意に減少したことが明らかになった。血中ビタミンD濃度も上昇しており、将来的に骨粗鬆症や骨折の発症リスク低減につながる可能性があるという。研究は東京大学医学部附属病院22世紀医療センターロコモ予防学講座の吉村典子氏らによるもので、詳細は8月27日付で「Archives of Osteoporosis」に掲載された。
ビタミンDは骨密度の維持に不可欠だが、世界的に血中25(OH)D濃度の低値が報告されており、世界的にビタミンD欠乏は広くみられ、とくに南アジア・中東で顕著である。さらに閉経後女性では欠乏率が高く、東アジアでも90%に達するとの報告がある。日本においても閉経後女性のビタミンD不足は深刻である。国内で実施されている「Research on Osteoarthritis/Osteoporosis against Disability(ROAD研究)」は、運動器疾患の予防を目的とした地域住民コホート研究である。2005~2007年調査では、ビタミンD不足・欠乏が9割以上と高頻度に認められ、その傾向は男性よりも女性で顕著であった。その後も同一地域で追跡調査が継続されており、本研究では調査開始から10年後のデータを用いて、ビタミンD欠乏の10年間の推移を明らかにすることを目的とした。
 骨粗鬆症に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
骨粗鬆症に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。ROAD研究のベースライン調査は2005~2007年に実施され、東京都板橋区(都市部)、和歌山県日高川町(山間部)、和歌山県太地町(沿岸部)の3地域から参加者を募った。都市部の参加者についてはベースライン時に骨密度測定が行われていなかったため除外し、本研究の解析対象は山間部および沿岸部の参加者1,690名とした。血液サンプルは1,683名(男性595名、女性1,088名)から採取され、血中25DおよびインタクトPTH(副甲状腺ホルモン)濃度を測定した。参加者は面接形式の質問票に回答し、骨密度測定とX線検査も受けた。第4回調査は2015~2016年に実施され、1,906名(男性637名、女性1,269名)が参加した。全参加者はベースライン調査と同一の評価を受けた。ビタミンD欠乏および不足は、それぞれ血中25D濃度が20ng/mL未満、20ng/mL以上30ng/mL未満と定義された。
平均血中25D濃度は、ベースラインで23.3 ng/mL、第4回調査では25.1 ng/mLとなり、有意な上昇が認められた(P<0.001)。ビタミンD不足および欠乏の有病率は、ベースラインでそれぞれ52.9%と29.5%であったのに対し、第4回調査では54.8%と21.6%となり、ビタミンD欠乏が有意に減少していた(P<0.001)。この傾向は男女ともに一貫して認められた。
骨密度に関しては、腰椎(L2–4)および大腿骨頸部のいずれも、第4回調査の方がベースライン調査より有意に高値を示した(腰椎P<0.001、大腿骨頸部P<0.05)。また第4回調査では、男女とも腰椎(L2–4)の骨粗鬆症有病率がベースラインより有意に低下していた(P<0.01)。
本研究について著者らは、「10年間隔の地域住民調査においてビタミンD欠乏症の有病率が有意に減少した。この好ましい傾向は、今後の骨粗鬆症および骨折発症率の低下に寄与する可能性がある」と述べている。
一方で、30~50代の女性では依然としてビタミンD欠乏症の割合が高く、この世代が今後閉経期を迎えて骨粗鬆症リスクの高い年齢層に入ってきた際には、将来的に骨粗鬆症の増加につながる可能性があると警鐘を鳴らしている。著者らは、この点を公衆衛生上の重要な課題として指摘した。
治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。
-
10月 06 2025 ロボット支援直腸がん手術、術後1日目のCRPで合併症予測が可能に
術後合併症や感染症への対応には、早期発見と迅速な対処が求められる。今回、直腸がんに対するロボット支援下直腸手術(RARS)後の合併症リスクが、術後1日目のC反応性蛋白(CRP)値で予測できるとする研究結果が報告された。術後早期のCRP測定が、高リスク患者の見極めや迅速な介入に役立つ可能性があるという。研究は国立病院機構福山医療センター消化器・一般外科の寺石文則氏らによるもので、詳細は8月28日付けで「Updates in Surgery」に掲載された。
RARSは、骨盤内の限られた視野で高い操作性を発揮し、従来の腹腔鏡手術や開腹手術と同等かそれ以上の成績を示すことが報告されている。しかし、依然として術後合併症は患者予後を左右する大きな課題であり、早期に高リスク患者を見極めることが重要だ。炎症マーカーであるCRPは大腸手術後の合併症予測に有用とされるが、ロボット支援手術における術後早期のCRP値の予測的価値は十分に検討されていない。このような背景を踏まえ著者らは、RARS後の合併症リスク因子を解析し、特に術後1日目のCRP測定の有用性を評価することを目的とした後ろ向きコホート研究を実施した。
 治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら
郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。本解析では、岡山大学病院にて、2020年9月から2025年1月にかけて、原発性直腸がんに対して待機的にロボット支援手術を受けた連続症例を対象とした。血清CRP値は、術前および術後1日目と4日目に測定された。主要評価項目は、手術後30日以内に発生したすべての合併症の有無であり、Clavien–Dindo(C–D)分類に基づいて評価した。群間比較は、連続変数についてはt検定またはMann-Whitney U検定、カテゴリ変数についてはカイ二乗検定またはFisherの正確確率検定を用いた。また、単変量解析で有意な因子や臨床的に重要な因子を多変量ロジスティック回帰モデルに投入し、術後1日目のCRPを含む独立した合併症予測因子を特定した。さらに、ROC解析で最適カットオフ値を算出し、Youden指数で評価した。
追跡期間中に直腸がんに対してロボット支援手術を受けた患者117名が本研究の対象となった。平均年齢は66歳で、男性は59.0%を占めた。術後合併症は26名(22.2%)に発生し、腸閉塞(10例)、腹腔内膿瘍および吻合不全(7例)、リンパ漏(2例)などが認められた。手術後30日以内の死亡はなかった。単変量解析により、これらの合併症は高齢、ASAスコア(米国麻酔学会の全身状態評価)の上昇、術前補助療法、ストーマ造設、手術時間の長さ、術後1日目・4日目のCRP値上昇などと有意に関連することが示された。これらの因子を含めた多変量ロジスティック回帰分析を行った結果、術後1日目のCRP値は術後全体の合併症の強力かつ独立した予測因子であることが明らかとなった(調整オッズ比 0.77、95%信頼区間〔CI〕 0.63~0.93、P<0.01)。
5分割交差検証を用いたROC解析では、AUCは0.735(ブートストラップ法によるバイアス補正95%CI 0.544~0.848)であった。術後1日目のCRPの最適カットオフ値は5.63 mg/dLで、この値でYouden指数は最大(0.484)となり、感度 0.615、特異度 0.868を示した。これらの結果から、術後1日目のCRP測定は、直腸がんに対するロボット支援直腸手術後の合併症を予測する有用かつ独立したバイオマーカーであることが示唆された。
本研究について著者らは、「術後1日目のCRP値測定を術後管理に組み込むことで、高リスク患者の早期発見が可能となり、迅速な介入や最終的な手術成績の改善につながる可能性がある」と述べている。
また著者らは、今後の研究において前向きかつ多施設での検証が必要であることを強調するとともに、CRPと他のバイオマーカーを組み合わせることで、予測精度をさらに高められる可能性があることにも言及している。
治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。
HOME>10月 2025