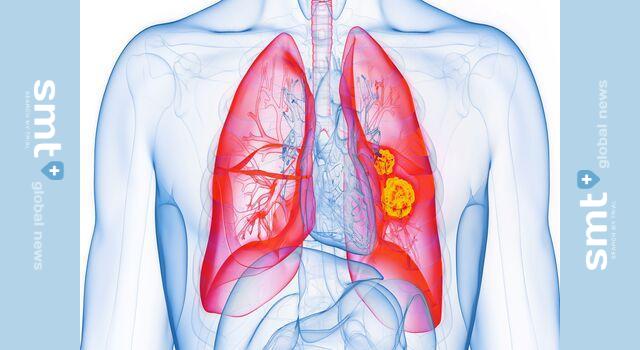-
2月 09 2026 祝日や年末に外傷は増える? 国内データが示す外傷の季節性
救急外来や外傷医療の現場では、患者数の増減が医療提供体制に大きな影響を与える。これまで外傷の発生には季節性があることが知られてきたが、祝日や年末年始といった社会・文化的イベントとの関係を、長期かつ日単位で検証した研究は限られていた。日本全国38万人超の外傷データを解析した本研究では、ゴールデンウィークや年末など特定の時期に外傷が増加する一方で、お盆や年始には減少することが明らかになった。研究は、総合病院土浦協同病院救命救急センター・救急集中治療科の鈴木啓介氏、遠藤彰氏によるもので、詳細は12月18日付で「Scientific Reports」に掲載された。
外傷は世界的に主要な死因・障害原因であり、医療・社会に大きな負担を与えている。外傷発生の季節性や祝日の影響はこれまでにも報告されてきたが、多くは短期間の観察にとどまっていた。比較的均質な文化・行動様式を持つ日本では、ゴールデンウィークやお盆、年末年始など生活リズムが大きく変化する時期が存在し、加えて自殺は春から夏に多いという季節性も知られている。本研究は、18年間にわたる全国外傷データを日単位で解析し、こうした年間を通じた行動パターンと外傷・自殺企図の発生動向を包括的に評価することで、医療資源配分や予防戦略の最適化に資する知見を得ることを目的とした。
 【治験について相談したい方へ】
【治験について相談したい方へ】
治験情報の探し方から参加検討まで、専門スタッフが一緒にサポートします本研究では、2004年1月から2021年12月までの日本外傷データバンク(JTDB)を用いて後ろ向き解析を行った。JTDBは、少なくとも1部位で簡易傷害度スケール(AIS)3以上を有する重症外傷患者のみを登録対象とする全国データベースである。JTDBからは、年齢、性別、受傷日および受傷機転、外傷分類、外傷重症度スコア(ISS)、AIS、退院時転帰などの変数を抽出し、受傷日(年月日)が特定可能な外傷患者を対象とした。対象患者は搬送日ごとに分類し、1年365日それぞれの日単位で解析した。日別の患者数、外傷重症度、自殺企図、死亡率を評価し、周期関数を組み込んだ負の二項回帰、外傷重症度で調整したロジスティック回帰、ならびに一般化極端スチューデント化偏差(GESD)検定を用いて外れ値を同定した。
本研究では38万3,473人が解析に含まれた。解析の結果、外傷症例数は年間を通じて大きく変動し、9~12月に多い傾向が示された。ゴールデンウィーク(4月29日~5月5日)や、文化の日(11月3日)、体育の日(現スポーツの日:10月10日)、年末(12月28~29日)にピークがみられた一方、お盆期間(8月中旬)、特に8月15日前後や年始には減少し、最少は3月7日(886例)、次いで1月3日(898例)であった。
自殺企図は21,637例(全体の5.6%)で、5~6月および8月下旬~9月に増加し、10~12月に減少するなど、全外傷とは異なる季節性が認められた。
日別死亡率は平均9.6%で、年間を通じた変動は小さく、明確な季節性や有意な外れ値は認められなかった。また、2004~2021年の全期間を通じて、外傷症例数の季節変動パターンは概ね一貫していた。
著者らは、「日本の外傷症例数は、祝日や季節的な生活習慣に沿った一定の年間変動を示した。自殺企図は独自の季節性を示したが、外傷全体の症例数や死亡率に大きな影響はなかった。本研究は、外傷医療リソースの計画や予防策を検討するうえで、行動や社会的要因を考慮することの重要性を示している」と述べている。
なお、本研究の限界として、重症外傷患者に限定した解析であり、日本特有の文化的背景を反映している点や、後ろ向き研究のため、祝日と外傷発生の因果関係を直接示せない点などを挙げている。
治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。
-
2月 09 2026 認知症の有病率と発症率は2012年以降低下か――久山町研究からのメッセージ
高齢化が進む中でも、認知症は必ずしも増え続けるとは限らない。今回、久山町研究の長期疫学データから、認知症の有病率と発症率が2012年以降低下していることが示された。健診と保健指導が継続的に行われてきた地域特性を踏まえると、本研究は生活習慣病管理と認知症予防の関係を考える上で、重要な示唆を与える。研究は、九州大学大学院医学研究院精神病態医学分野の小原知之氏、同衛生・公衆衛生学分野の二宮利治氏らによるもので、詳細は、12月29日付で「Alzheimer’s Research & Therapy」に掲載された。
高齢化が進む中、認知症の増加とその社会的負担は大きな課題とされてきた。一方で、認知症の有病率の推移については、増加を示す研究と横ばい・低下を示す研究が混在しており、見解は一致していない。こうした違いを理解するには、認知症の有病率だけでなく、発症率や発症後の生存率を併せて検討する必要がある。特にアジア地域では、同一地域を長期間追跡した研究は限られている。久山町研究では、1985~2012年にかけて認知症有病率が増加し、その背景として認知症発症率の上昇と発症後生存率の改善が関与していることが報告されている。本研究はその知見を踏まえ、37年にわたる調査データを用いて、日本の地域住民における認知症の有病率、発症率、発症後生存率の2012年以降の推移を検討した。
 【認知症の治験について相談したい方へ】
【認知症の治験について相談したい方へ】
治験情報の探し方から参加検討まで、専門スタッフが一緒にサポートします久山町研究は、1961年から福岡県久山町の住民を対象に継続されている、日本を代表する地域住民コホート研究である。国勢調査によると、久山町の年齢構成や職業構成、栄養摂取状況は、過去60年間にわたり日本全体とほぼ同じ水準にあるとされている。本研究では同地域において、65歳以上の住民を対象に、1985年、1992年、1998年、2005年、2012年、2017年、2022年の7時点で認知症に関する悉皆調査を実施した(全ての受診率:92%以上)。さらに、認知症のない65歳以上の住民を対象に、1988年(803人)、2002年(1,231人)、2012年(1,519人)の3つのコホートを設定し、それぞれ10年間追跡した。認知症有病率の推移はロジスティック回帰モデルを用いて検討した。認知症の発症率と発症後生存率については、Cox比例ハザードモデルを用いて性別と年齢を調整してコホート間で比較した。
認知症の有病率は、1985年から1998年まで横ばいで推移したが、その後は2012年にかけて有意に上昇した(1985年6.7%、1992年5.7%、1998年7.1%、2005年12.5%、2012年17.9%、傾向P値<0.01)が、その後2017年15.8%、2022年12.1%と有意に減少した(傾向P値<0.01)。これらの関係は年齢で調整しても同様の傾向が認められた。
認知症の有病率は、発症率と発症後の予後によって規定される。この有病率が時代とともに変化した要因を明らかにするために、1988年、2002年、および2012年のコホートを比較した。その結果、年齢・性別調整後の認知症発症率は、1988年コホート(1988~1998年)から2002年コホート(2002~2012年)にかけて有意に上昇した(調整ハザード比〔aHR〕1.68、95%信頼区間〔CI〕1.38~2.06)。一方、同発症率は2002年コホートから2012年コホート(2012~2022年)にかけて有意に低下した(aHR 0.60、95%CI 0.51~0.70)。
つぎに、認知症発症後の予後の時代的変化を検討したところ、認知症発症後5年生存率は、1988年コホートから2002年コホートにかけて有意に改善していた(47.3%から65.2%、P<0.01)。一方、同生存率は2002年コホートから2012年コホートにかけては明らかな変化を認めなかった(65.2%から58.9%、P=0.42)。
こうした結果から、2000年代になって認知症有病率が急増した背景には、認知症の発症率が時代とともに上昇したことに加えて、認知症発症後の予後が改善したことがあるとみられる。一方、2012年以降、認知症の有病率が低下した背景には、近年のコホートで認知症発症率が低下したことが影響している可能性がある。
著者らは、「本研究において認知症の有病率と発症率が2012年以降減少傾向にある背景には、高血圧や糖尿病など危険因子の管理状況の改善と喫煙率の低下や運動習慣の増加など健康的な生活習慣の普及が関与している可能性が考えられる。高齢化が進む社会において、認知症の発症リスクを低減してその社会的負担の増大を抑制するためには、生活習慣病の予防とその適切な管理に加え、健康的な生活習慣を心がけることが重要」と述べている。
なお、著者らは、本研究の限界点として、単一地域での調査であるため一般化が難しい点を挙げている。また、近年の診断環境の変化や頭部外傷や難聴など未評価の危険因子があること、COVID-19流行が結果に影響した可能性を述べている。
軽度認知障害(MCI)のセルフチェックに関する詳しい解説はこちら

軽度認知障害を予防し認知症への移行を防ぐためには早期発見、早期予防が重要なポイントとなります。そこで、今回は認知症や軽度認知障害(MCI)を早期発見できる認知度簡易セルフチェックをご紹介します。
-
2月 02 2026 肝機能の「長期的な変化」が糖尿病リスクを予測か──日立コホート研究
2型糖尿病は、発症前の段階でいかにリスクを捉えるかが重要となる。健康診断では肝機能検査が毎年行われているが、その数値は多くの場合、一過性の変動として単年ごとに評価されるにとどまってきた。日立コホート研究による約2万人・13年超の追跡解析から、若年期に一時的な肝機能高値を示し、その後数値が改善している人においても、将来の2型糖尿病リスクが高い傾向にあることが示された。肝機能の「一時点の値」ではなく長期的な変化のパターンに着目する重要性が浮き彫りになった。研究は、東海大学医学部基盤診療学系の深井航太氏らによるもので、詳細は12月14日付で「Scientific Reports」に掲載された。
肝機能障害と2型糖尿病との関連は、インスリン抵抗性や脂肪肝を介した双方向の関係が示唆されている。アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、γ‐グルタミルトランスフェラーゼ(GGT)などの肝酵素は日常診療で広く測定されている指標であるが、これまでの研究の多くは単一時点の測定値に基づいており、肝機能の長期的変化を十分に捉えられていなかった。本研究では、年次健診データを有する日立コホート研究を用い、肝酵素の推移パターンを分類し、2型糖尿病発症との関連および基準値超過の頻度が与える影響を検討することを目的とした。
 【2型糖尿病の治験について相談したい方へ】
【2型糖尿病の治験について相談したい方へ】
治験情報の探し方から参加検討まで、専門スタッフが一緒にサポートします日立コホート研究は、茨城県日立市の準都市工業地帯にある日立健康管理センタの従業員に提供される企業の年次健康診断に基づいている。本研究では、日立コホート研究において、ベースライン時に2型糖尿病を有さない30~64歳の2万4,380人を対象とし、計29万6,171件の健康診断データを解析した。肝機能酵素として、ALT、AST、GGTを年1回測定した。肝酵素の長期推移をトラジェクトリ解析(group-based trajectory modeling;GBTM)により分類し、各軌跡群と2型糖尿病発症との関連をロジスティック回帰で検討した。年齢・性別、代謝指標、生活習慣因子を調整した。
ベースライン時の平均年齢は42.9歳だった。平均12.8年の追跡期間中に、3,840人(15.8%)が2型糖尿病を発症した。トラジェクトリ解析により、ALTは6群、ASTは3群、GGTは4群の推移パターンが同定された。
ALTが持続的に高値を示す群や、若年成人期に上昇を示す推移群では、2型糖尿病発症リスクが有意に高かった。ALTが一貫して高値で推移した群(群6)のオッズ比は7.97(95%信頼区間〔CI〕 7.40~8.57)、若年成人期に高値を示した群(群5)では4.23(95%CI 4.00~4.48)であり、いずれも一貫して低値の群(群1)と比べて高リスクであった(傾向P値、P<0.01)。
さらに、ALTおよびASTが基準値を繰り返し超過するほど2型糖尿病リスクは上昇し、閾値が高いほど、また超過頻度が多いほど関連は強かった。GGTについては、ALTほど強い関連ではなかったものの、基準値を2回以上超過した場合、2型糖尿病リスクが2倍以上に上昇していた。
著者らは、「ALTの高値が持続している人はもちろん、『以前高かった』人でも糖尿病発症リスクは約4倍に上昇していた。健康診断の結果は単年値ではなく経時的な推移を重視すべきであり、若年期からリスクの兆候を捉えることが、将来的な予防につながる可能性がある」と述べている。
なお、本研究の限界として、特定コホートに基づくため一般化が制限されること、薬物治療や生活習慣の変化などの影響が考慮されていない点などを挙げている
糖尿病のセルフチェックに関する詳しい解説はこちら

糖尿病でいちばん恐ろしいのが、全身に現れる様々な合併症。深刻化を食い止め、合併症を発症しないためには、早期発見・早期治療がカギとなります。今回は糖尿病が疑われる症状から、その危険性を簡単にセルフチェックする方法をご紹介します。
-
2月 02 2026 全身治療後のサルベージ手術で示された、進行肺がんの新たな長期生存の可能性
進行した非小細胞肺がん(NSCLC)では、初診時に切除不能と判断される症例が多く、治療の主軸は全身治療に置かれてきた。しかし、治療反応が良好な一部の患者に対して、全身治療後に外科切除を行うサルベージ手術の意義は十分に検討されていない。今回、全身治療後にサルベージ手術を行った高度に選択された症例を解析した結果、進行肺がんでも長期生存が現実的となる可能性が示された。研究は愛知県がんセンター呼吸器外科部の瀬戸克年氏、坂倉範昭氏らによるもので、詳細は12月17日付で「Thoracic Cancer」に掲載された。
分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬の登場により、進行NSCLCに対する全身治療成績は大きく向上している。これに伴い、初診時には切除不能と判断された症例でも、全身治療後に病変が局在化・縮小し、根治を目的としたサルベージ手術が行われるケースが増えている。一方、薬物療法後の手術は治療関連線維化など特有の課題を伴い、長期予後への真の影響については十分なエビデンスがない。こうした背景から本研究は、全身治療後にサルベージ手術を行ったNSCLC症例を後ろ向きに解析し、その安全性と腫瘍学的成績、臨床的意義を検討した。
 【肺がんの治験について相談したい方へ】
【肺がんの治験について相談したい方へ】
治験情報の探し方から参加検討まで、専門スタッフが一緒にサポートします本研究では、2014年1月1日から2024年12月31日にかけて愛知県がんセンターで治療を受けた、初診時に切除不能と診断されたNSCLC患者を対象とした。このうち、化学療法、分子標的治療、免疫療法のいずれか、またはそれらの併用後に、根治目的のサルベージ手術を受けた32例を後ろ向きに解析した。主要評価項目は全生存期間(OS)とし、副次評価項目として無再発生存期間(RFS)、重篤な合併症(Clavien–Dindo分類Ⅲa以上)、およびR0切除(完全切除)率を設定した。生存解析にはKaplan–Meier法およびlog-rank検定を用いた。
年齢中央値は61.0歳で、男性が約3分の2を占めた。ECOG Performance Status(PS)は30例が0、残る2例も1で、PS 2以上の症例は認めなかった。初診時に切除不能と判断された理由は遠隔転移が最多で、次いでN3リンパ節転移や高度N2病変などであった。手術前に行われた全身治療の治療ライン数中央値は1で、細胞障害性抗がん薬、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬が症例に応じて使用されていた。
追跡期間中央値40.1か月時点で、OSの中央値には到達せず、RFSの中央値は49.9か月であった。5年OS率は75.0%(95%信頼区間〔CI〕 51.6~88.3)、5年RFS率は46.3%(95%CI 26.3~64.2)であった。
サルベージ手術の内訳は、肺葉切除術21例(65.6%)、区域切除術6例(18.8%)、楔状切除術5例(15.6%)であり、R0切除は26例(81.3%)で達成された。
合併症は全体で4例(12.5%)に発生した。重篤な合併症は1例で、胸膜癒着術を要する遷延性気漏であった。術後90日以内の死亡は認められなかった。
さらに、術後24か月以内に再発または死亡を認めなかった症例を予後良好群(18例)、認めた症例を予後不良群(14例)とし、探索的に各因子について単変量解析を行った。その結果、腺がんのみが有意に良好な予後と関連していた(88.9% vs. 35.7%、P=0.003)。
著者らは、「初診時に切除不能と判断されたNSCLC患者において、全身治療後に行われたサルベージ手術が、安全性および有効性の両面で良好な成績を示した。追跡期間中央値40.1か月における5年OS率は75%、5年RFS率は46%であり、厳密に選択された症例では、サルベージ手術が生存期間延長を目指す治療選択肢となり得る可能性が示唆された」と述べている。
その一方で、単施設・後ろ向き研究である点に加え、全身治療のみで管理された症例や、全身治療後に外科へ紹介されたものの手術に至らなかった症例が含まれていないことから、選択バイアスの影響は否定できないとしている。このため、今後は多施設前向き研究による検証が必要であると述べている。
肺がんのセルフチェックに関する詳しい解説はこちら

肺がんは初期の自覚症状が少ないからこそ、セルフチェックで早めにリスクを確かめておくことが大切です。セルフチェックリストを使って、肺がんにかかりやすい環境や生活習慣のチェック、症状のチェックをしていきましょう。
HOME>2月 2026